2025年3月からマイナ免許証の運用がスタート!メリットや注意点について解説
従来の運転免許証からマイナ免許証への切り替えが可能に
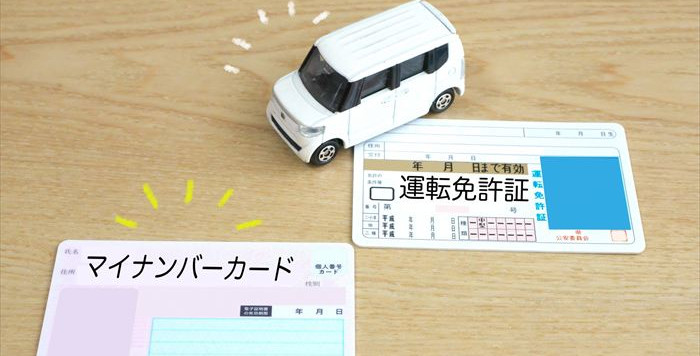
仕事で運転する機会がある場合、従業員は当然免許証を携帯することになります。
しかし、2025年3月24日から従来の運転免許証から「マイナ免許証」への切り替えが可能となりました。
マイナ免許証は従来の運転免許証とどのような違いがあり、仕事にどのような影響が出る可能性があるのか、不安に感じる人もいるでしょう。
そこで今回は、マイナ免許証の特徴やメリット、注意点について解説していきます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
マイナ免許証とは?

マイナ免許証とは、マイナンバーカードに免許情報が記録されたもので、2025年3月24日から通常の運転免許証をマイナ免許証に切り替えられるようになりました。
運転免許証とマイナンバーカードを1つにまとめられるという特徴があります。
マイナ免許証の取得は任意
仕事で営業車を使用する場合、従業員に呼びかけてマイナ免許証に変更してもらう必要があるのか、気になる人もいるでしょう。
結論からいえば、マイナ免許証の取得は任意であり、すぐに変更してもらう必要はありません。
2025年3月24日からマイナ免許証の運用がスタートしますが、だからといって従来の運転免許証がなくなるわけではありません 。
従来の運転免許証をこれまでと同じように保有したり、新たにマイナ免許証へ変更したりすることも可能です。
マイナ免許証にはどのような情報が記録される?
マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップに免許情報が記録されることになり、具体的には、以下の項目が記録されます。
-
- マイナ免許証の番号
- 免許の年月日および有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件にかかる事項
- 顔写真
これらの項目はもともと運転免許証の券面に記載されていたものですが、すべてICチップの中に記録されます。
そのため、マイナ免許証の券面にはこれらの情報が記載されておらず、ICチップを読み取ることで確認することが可能です。
マイナ免許証を取得するメリット

マイナ免許証を取得すると、運転者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここで、マイナ免許証を取得するメリットを解説します。
オンライン講習が受けられる
マイナ免許証を取得していると、オンライン講習が受けられるようになります。免許証の更新時には法定講習を受ける必要があります。
法定講習の時間は各免許の区分によっても異なりますが、最低でも30分はかかるでしょう。
さらに適性検査や更新審査、写真撮影などもあるため、最終的に2~3時間はかかってしまうことが多いです。
しかし、マイナ免許証を取得している人で、なおかつ優良運転者・一般運転者に該当している場合は、スマートフォンなどから好きな時間にオンラインで講習を受けられます。
視力検査や写真撮影は免許センターなどで受ける必要があるものの、先にオンライン講習を受けてしまえば更新手続きにかかる時間を短縮できます。
住所変更の手続きなどがワンストップで受けられる
これまでは引っ越して住所が変更になった際に、記載事項変更届や新住所がわかる書類、運転免許証を警察署または運転免許更新センターなどに持参する必要がありました。
しかし、マイナ免許証を取得していて、あらかじめ必要な手続きをとっていれば、住所や本籍、氏名などに変更があった場合でも、警察への届け出は不要です。
ただし、このワンストップサービスが受けられるのは、マイナ免許証のみを保有する人に限られます。
例えば、運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちをしている人は利用できないので、注意が必要です。
更新手数料などがお得になる
運転免許証を新規で取得する際や更新手続きを行う場合、運転免許証よりもマイナ免許証のほうが手数料はお得になります。
取得パターンごとの手数料の違いは、以下のとおりです。
| マイナ免許証のみ | 運転免許証のみ | 運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち | |
| 新規免許取得時の手数料 | 1,550円 | 2,350円 | 2,450円 |
| 更新時の手数料 | 2,100円 | 2,850円 | 2,950円 |
更新手続きの迅速化と申請期間が延長される
マイナ免許証のみ、または運転免許証と2枚持ちしていて、なおかつ優良運転者・一般運転者に該当している場合、住んでいる都道府県以外の警察署または免許センターであっても、運転免許証の更新手続きが迅速化されます。
その上、マイナ免許証のみの更新手続きであれば、即日で手続きが完了します。
ただし、2枚持ちの人は従来の運転免許証はこれまでと同様に日数がかかってくるため、後日交付を受けなくてはなりません。
また、これまでは運転免許証を更新する期間は更新期間初日から誕生日までの間に申請しなくてはなりませんでした。
しかし、更新期間初日から免許証などの有効期間の末日までに延長されました。
申請期間の延長によって、ゆとりをもって更新手続きが行えるようになり、仕事などで忙しい人も調整しやすくなります。
携帯するカードが1枚で済む
日頃から運転をしていてマイナンバーカードも保有している場合、2枚を携帯していることになります。
しかし、マイナ免許証に切り替えれば、マイナンバーカードに運転免許証の情報が記録されるため、1枚携帯していれば良いことになります。
携帯するカードを減らせるため、運転免許証は持っていたのにマイナンバーカードを忘れてしまった、といった事態も回避することが可能です。
マイナ免許証の取得パターン

マイナ免許証の取得パターンは、主に3つあります。それぞれの特徴について解説します。
マイナ免許証のみ
マイナ免許証のみの場合、上記で挙げたメリットの多くを受けられます。
特に住所や氏名変更があったとしても、事前に手続きを済ませておけばわざわざ免許センターなどに行かなくても役所でワンストップ手続きが可能になるのは嬉しいポイントです。
また、従来の運転免許証とは違い、更新手続きの際にも新たに発行する必要がないことから、更新手続きの際にかかる費用も安く抑えられます。
運転免許証のみ
これまでと同様、運転免許証だけを保有するパターンもあります。運転免許証の券面には運転者の情報が詳しく掲載されており、一目で確認することが可能です。
従来の使い方のままで利用できることから、引き続き写真付き身分証として活用できます。
ただし、マイナ免許証を取得していないことでオンライン講習を受講できなかったり、更新時の手数料がお得にならなかったりするので注意が必要です。
特に更新時にかかる費用は、運転免許証のみだと手数料2,850円+講習料で3,000円以上かかってきます。
マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち
マイナ免許証と運転免許証を2枚持ちすることも可能です。2枚持ちをするメリットは、マイナ免許証と運転免許証のメリットを両方享受できる点が挙げられます。
マイナ免許証を保有していることでオンライン講習が受講でき、さらに運転免許証の提示が求められる場所で困ることもありません。
また、普段の運転時にはマイナ免許証か運転免許証のどちらかだけ携帯していれば良いため、どちらかを忘れてしまった場合でも免許不携帯にはなりません。
ただし、マイナ免許証のみ・運転免許証のみと比較して更新手数料は一番高額です。これは2枚とも更新手続きが必要となるためです。
また、住所変更時にはマイナンバーカードの手続きに加え、運転免許証側の手続きも必要となります。
マイナ免許証における注意点
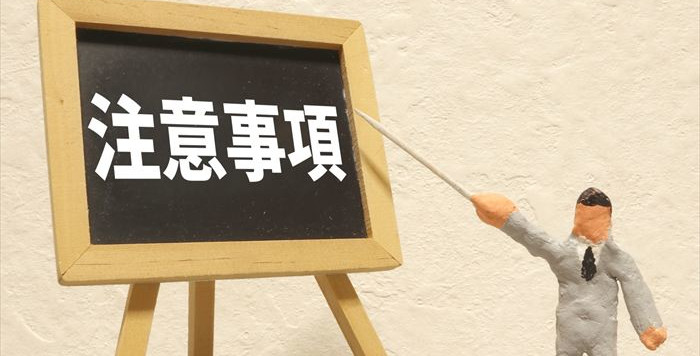
マイナ免許証を取得するにあたって、注意すべきポイントがいくつかあります。ここで、マイナ免許証における注意点も把握しておいてください。
マイナンバーカードを更新する際は免許情報の再記録が必要
マイナ免許証を取得してからマイナンバーカードを市区役所などで更新した場合、更新後のマイナンバーカードに免許情報は引き継がれません。
そのため、マイナンバーカードを更新する際には免許情報の再記録が必要となります。
もし免許情報の再記録を忘れていると、マイナ免許証を取得していたとしても免許証不携帯の交通違反に該当してしまうため、経営者は従業員に周知させておくと安心です。
免許情報の再記録は免許センターで行うことができ、手数料は1,500円かかります。警察署では再記録の手続きができないので注意してください。
なお、2025年秋頃に更新後のマイナンバーカードにも免許情報が引き継がれる予定となっています。
免許情報を確認するにはマイナポータルか読み取りアプリが必要
マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップの中に免許情報が記録されることから、目視ですぐに免許情報を確認することはできません。
免許情報を確認したい場合には、マイナポータルにログインするか、マイナ免許証読み取りアプリが必要となります。
そのため、仕事上運転免許証を提示する機会が多いケースでは、券面に情報が記載されていないマイナ免許証よりも従来の運転免許証のほうが良い場合もあります。
マイナ免許証の取得を考えている従業員がいたら、そのような注意点も共有し、2枚持ちという手段があることも伝えてみてください。
一部のレンタカー会社しか対応していない
上記で「仕事上運転免許証を提示する機会が多いケース」と紹介しましたが、例えば、レンタカーを利用するケースが挙げられます。
地方へ赴く機会がある場合、レンタカーを利用するためには運転免許証を提示しなくてはなりません。
しかし、マイナ免許証は運用後も一部のレンタカー会社しか対応しておらず、対応しているレンタカー会社でも自分のマイナ免許証読み取りアプリを使って免許情報を提示する必要があります。
レンタカー会社によって対応に違いがあるため、仕事でよく利用するレンタカー会社があれば、マイナ免許証に対応しているかどうか事前に確認しておいてください。
再発行するのに時間がかかる
万が一マイナ免許証を紛失してしまった場合、再発行を行うことになりますが、従来の運転免許証と比べて再発行するのに時間がかかってしまいます。
これまでは運転免許試験場か免許センターなどで手続きをすれば、基本的には即日で再発行を受けられました。
しかし、マイナンバーカードを再発行するためには通常1~2カ月もの期間を要することになります。
緊急事態の場合は期間が短縮されるものの、それでも最低5日程度はかかってしまい、即日再発行とはなりません。
車を運転するためには免許証を携帯している必要があることから、再発行されるまでの1~2カ月間は車を運転できないことになってしまいます。
すぐにでも運転免許証が必要という場合には、従来の運転免許証なら原則即日発行も可能となるため、最寄りの警察署などに相談してみてください。
マイナ免許証とマイナンバーカードの有効期間が異なっている
マイナ免許証とマイナンバーカードは、免許情報がICチップに記録されているか、記録されていないかの違いしかないため、有効期間が同じように感じてしまうかもしれません。
しかし、実際にはマイナ免許証とマイナンバーカードは有効期間が異なっており、それぞれ有効期間を把握した上で更新手続きを行う必要があります。
特にマイナ免許証は券面に有効期間の末日が表記されていないため、更新手続きを忘れないように注意してください。
海外で運転する際には従来の免許証が必要なケースもある
仕事で海外出張があり、海外で運転する機会がある場合は、マイナ免許証ではなく従来の運転免許証が必要となるケースもあります。
これはカードの券面に免許情報が表示されていないことから、現地で無免許と判断される可能性があるためです。
海外で運転をする機会がある場合は、従来の運転免許証を取得して渡航先の国や地域に持っていくようにしてください。
マイナ免許証に関するQ&A

最後に、マイナ免許証に関するQ&Aについて解説します。
マイナ免許証はどこで手続きを行える?
マイナ免許証を取得したい場合、住んでいる地域の免許センターや一部警察署で手続きを行うことが可能です。
ただし、新規取得や更新手続きなど、行う手続きによってできる施設とできない施設があります。
| 運転免許試験場 | 免許センター | 指定警察署 | 指定外警察署 | |
|---|---|---|---|---|
| 免許更新 | ○ | ○ | ○ | - |
| 保有状況の変更のみ | ○ | - | - | - |
| 新規取得・併記 | ○ | - | - | - |
| 運転経歴証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 記載事項の変更 | ○ | - | - | - |
| 再発行(遺失・毀損など) | ○ | - | - | - |
| 失効(再取得) | ○ | - | - | - |
マイナ免許証にするのに必要なものはある?
運転免許証を取得していて、マイナ免許証のみ、または2枚持ちにしたい場合、基本的にはマイナンバーカードと運転免許証を持参する必要があります。
ただし、マイナポータルと連携させたい場合には、署名用電子証明書の提出が必要です。
署名用電子証明書の提出はマイナポータルから行うことになりますが、免許センターなどで6~16ケタのパスワードを入力する必要があるため、確認できるものもあると安心です。
マイナンバーカードが失効するとマイナ免許証も失効する?
マイナンバーカードが失効してしまった場合、マイナ免許証も失効するのか不安に感じる人もいるかもしれません。
マイナンバーカードが失効しても、マイナ免許証の免許情報まで失効するわけではないので安心してください。
ただし、マイナ免許証の有効期間内に更新手続きを行う場合、マイナンバーカードが失効状態にあると更新手続きは行えません。
まずはマイナンバーカードの更新手続きを済ませてから、マイナ免許証の更新手続きを行うようにしてください。
まとめ・マイナ免許証の注意点も把握して取得するか検討しよう
マイナ免許証はマイナンバーカードとの一体化によってオンライン講習を受講できたり、住所・氏名を変更する際の手続きが不要になったりするなど、様々なメリットが得られます。
ただし、券面に免許情報が表示されないことで不便に感じるシーンや、紛失した際に再発行するまで時間がかかるなど、注意しなくてはいけないこともあります。
従業員の中でマイナ免許証の取得を検討している人がいる場合は、仕事にどのような影響があるかも考慮しつつ慎重に検討できるよう、経営者側もマイナ免許証について把握しておくことが大切です。
創業手帳(冊子版)では、様々な業態に影響するような新制度の解説なども掲載しています。経営・ビジネスに役立つ情報が揃っているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)





































