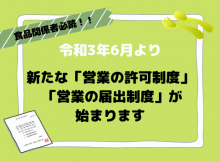2025年4月に車検制度が変更!社用車はどのような影響を受ける?
社用車の車検前に変更点を確認しよう!

自動車に乗る以上、車検は避けて通れません。車検が切れた車は公道を走ることが認められないため、社用車の車検が切れれば事業にも支障をきたします。
企業によっては社用車の台数も多く車検の手続きも煩雑になってしまうことがあります。
ここでは、2025年4月の車検制度の変更について説明していきます。車検に関わる問題は会社の信用にもかかわるのでしっかり理解しておいてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【2025年4月1日施行】車検制度の変更点

車検は、正式には「自動車検査登録制度」と呼ばれ、道路運送車両法で定められています。
公道を走行する車には定期的な検査である車検が義務付けられていて、車検では車が安全基準や環境基準を満たしているかを確認されます。
車検の基準に満たない場合には、不合格箇所の整備・修理をして再検査が必要です。
2025年4月には、車検制度に大きな変更が加わりました。ここでは、どのような点が変更になっているのかまとめています。
車検の受検期間が拡大
2025年4月の車検制度変更によって、車検受検期間が拡大されました。
車検期間が前倒しになり、これまでよりも早い有効期限満了日の2カ月前から車検手続きを受けられるよう変更されています。
これまでは、有効期限満了日の1カ月前から受検できてましたが、2カ月前からに変更されたため、より車検の依頼スケジュールを組みやすくなりました。
受検期間が拡大した背景
車検の受検期間が前倒しになった背景には、車検有効期限が集中する期間に整備工場などの業務が課題になっていたことがあります。
毎年3月は転居や決算を理由に車両の購入、買い替えが増えます。
その結果、車検の需要が一時期に集中して、繁忙期には整備スタッフの労働時間の長期化、労働負担が増大していました。
業務や負担が一定期間に集中してしまえば、サービスの質の低下や労働人口の減少につながります。
そこで車検の受検期間を長くすることによってピークを分散させれば、整備士がより均等な作業配分で対応可能です。
車検を受ける側も受検期間拡大によって車検の予約を取りやすくなり、混雑や長い待ち時間を避けられます。
受検期間が拡大するメリット
車検の受検期間が拡大することによって、整備現場の負担が軽減されます。
また、依頼する側も混雑期を避けやすくなり、スケジュールを組み立てやすくなる点がメリットです。
これらのメリットは、単純に車検を受けやすくなるだけではありません。
今までよりクオリティが高い車検を期待できる上、早期車検のインセンティブが拡大される可能性もあります。
車検の品質は車の安全性に関わる部分なので軽視できません。受検期間の拡大によって、より高い品質の車検をお得に受けられます。
さらに、車検満了日ギリギリに受ける車検は、そのタイミングで混雑していると車検の予約が取れずに車検切れになってしまうリスクがありました。
受検期間が拡大することによって、こうしたリスクも低くなっています。
自賠責保険の更新期間も拡大
自動車を所有していれば、必ず自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責保険は、事故を起こしてしまった時に被害者が負った身体的損害を最低限補償する公的保険制度です。
そのため、自賠責保険が切れた無保険状態での運転は危険であり、法で禁止されています。今までは、車検を受けた時に自賠責を保険を新しく契約するのが一般的でした。
2025年4月からは車検同様に自賠責保険も2カ月前から更新できます。
これによって期限ギリギリに更新手続きを行う必要がなくなり、余裕をもって更新できます。
車検制度の変更によって注意すべきこと

車検制度の変更により、車検の受検期間が2カ月になりました。運転する人や整備士にとってもメリットが多い変更ではありますが、注意すべきことがひとつだけあります。
それは、車検満了日によっては新制度が適用されないケースがある点です。
今回の受検期間拡大は4月1日からなので、3月31日に車検が満了する車に関しては2月28日からしか車検を受けられません。
4月1日に車検満了となる車は、2月1日から車検を受けられるものの、新制度の適用される前になるので次の車検満了日が早くなります。
車検満了日が5月1日の車が3月1日に車検を受けても同じです。
これを避けるには4月1日に車検を受けることになります。つまり、2カ月前に車検を受けても車検満了日が変わらないのは6月1日に満了の車からです。
新制度の適用になるかどうかの判断が複雑なため、混乱してしまうかもしれません。車検証の満了日を確認して不利益がないように車検日を設定してください。
車検制度における近年の変更内容

車検は、車が保安基準に適合しているかを定期的に確認する目的で実施されます。ここでは、近年の車検の変更内容について説明します。
ヘッドライトの審査方法の変更
ヘッドライトの検査は、原則としてロービームで実施します。しかし、ロービームで計測が難しい場合に限って今まではハイビームでの計測も認められていました。
しかし、2024年8月以降はロービームでの計測が義務となりました。
そのため、ロービーム検査のクリアが絶対条件となり、ヘッドライトの部品交換が必要になるケースも増えています。
ヘッドライトの交換の分だけ車検にかかる金銭的負担が増加する可能性が高い点には注意してください。
一部地域では運用面などの理由から移行が延期されているので、お住まいの地域の扱いを確認してください。
OBD(On-Board Diagnostics)検査の追加
自動車の技術が進み、自動ブレーキなど新しい安全技術が搭載された車が増えています。これらの機能は搭載されるだけでなく正しく作動するための検査やメンテナンスが欠かせません。
今までの車検は目視や測定器で実施するため、これらの機能について確認できませんでした。そこで2024年10月からは車検の項目としてOBD検査が追加されています。
OBDとは、On-Board Diagnosticsの略称で車載式故障診断装置と訳されます。
OBD検査の目的は車に搭載されている各種電子制御装置(ECU)の状態を監視して故障や不具合を記録することです。
検査の対象は、2021年(令和3年)10月以降に登場した新型車です。OBD検査は検査用スキャンツールを電子制御装置(ECU)に接続して実施します。
OBD検査の実施によって、1台あたり一律400円の法定手数料が追加されます。さらに不具合が検出されれば整備や修理の費用も必要です。
社用車の車検期間は車種で異なる

一般的に自家用車の車検期間は新規登録して初回は3年経過時、以降は2年ごとです。これは社用車であっても基本的に変わりません。
しかし、3,5,7ナンバーであれば自家用車と同じサイクルですが、4,1ナンバーの車は、初回車検は2年でそれ以降は毎年車検が必要です。
さらに事業用貨物、大型貨物については初回から毎年車検です。以下では車種ごとの車検のタイミングを表にまとめています。
| 車種 | ナンバー | 初回車検 | 2回目以降 |
| 自家用乗用車 軽乗用車 |
3、5、7ナンバー | 3年 | 2年 |
| 軽貨物自動車 大型特殊自動車 キャンピングカー |
4ナンバー 0、9ナンバー 8ナンバー |
2年 | 2年 |
| レンタカー | わナンバー | 2年 | 1年 |
| 大型貨物 | 1ナンバー | 1年 | 1年 |
| 小型貨物 中型貨物 |
4ナンバー 1ナンバー |
2年 | 1年 |
| バス・タクシー | 1年 | 1年 |
社用車の車検における検査内容

車検では、法律で義務付けられた項目の点検を実施して、必要があれば整備を行います。ここではどのような検査が行われるのか、項目ごとに紹介していきます。
同一性の確認
同一性の確認は、自動車検査証(車検証)に記載されている内容と持ち込まれた車両が同一であるかを確認することをいいます。
具体的には、エンジンに打刻された番号と車検証に記載された車台番号が同一かどうかを確認します。
これはエンジンが不正に改造されていないかの確認でもある作業です。検査官はボンネットを開けてエンジンルームを目視で確認しています。
ブレーキ系統
ブレーキ系統の検査では、ブレーキとサイドブレーキの効き具合をチェックします。
ブレーキパッド、ライニングの厚さ、ディスク・ドラムの摩耗や液漏れなどのチェックです。
ローラーの上にタイヤを乗せた状態で、ブレーキやサイドブレーキを操作する検査によって、車が確実に停止できるかどうかを確認する検査です。
停止できれば車検は通りますが、ブレーキは車の制動力を確保して安全を担保する役割があります。
ブレーキパッドが摩耗していて摩耗限界に近づいている場合には、車検を通ったとしても安全のために交換しておくようにおすすめします。
タイヤ・ホイール
タイヤ・ホイールの検査では、タイヤの空気圧や残り溝の不可さ、変摩耗やひび割れがチェックされます。
路面とのグリップを確保できていないと雨天時のスリップを防げません。
タイヤの溝が1.6mm未満になっている、スリップサインが出ているような場合は車検に通りません。
また、検査官がタイヤのナットやボルトを軽くたたき、締め付け具合に異常がないかをチェックします。
ライト類
ライト類の検査では、ヘッドライトやウィンカー、ブレーキランプの点灯状態を確認します。
きちんと点灯するかどうか、ウィンカーやハザードであれば点滅するかがチェック項目です。
ヘッドライトの光量と光軸の検査もあり、適正な明るさで適正な向きにライトが照らされているかチェックします。
点灯や点滅がない原因は電球切れが多く、電球の交換で解決することも多くあります。
夜間や悪天候時の視認性を確保するためライト類は重要なので、自身でも確認しておくようにしてください。
エンジン・ルーム点検
エンジンルーム点検では、エンジンオイルやブレーキオイル、冷却水とラジエター、バッテリーのように多くの項目がチェックされます。
バッテリーやスパークプラグのように一定期間で交換が必要な機器もあります。
エンジンオイルでチェックされるのは、オイル量が規定量を満たしているかどうか、劣化や漏れがないかどうかです。また、ブレーキオイルも漏れがないかチェックされます。
冷却水は、車検ごとに交換するケースが多いものの長期間交換不要の冷却水も登場しました。適正量があるか漏れがないかがチェック項目です。
バッテリー点検では、液量やパフォーマンス、充電機能が確認されます。さらにフューエルホースや各種ベルト類も劣化するため、自分でも適宜チェックしてください。
ステアリング系統
ステアリング系統の検査では、旋回時の異音、ハンドルのガタつきがないかチェックされます。車両の安定性を保って正確に操作するためステアリングは大切です。
タイヤとハンドルを繋いでいるタイロッドを保護するステアリングラックブーツに破れが出た場合には、車検を通過できません。
室内点検
車検では、車の室内点検も実施されます。シートベルトには損はないか、ヘッドレストがあるか、電灯が点滅かどうかも項目です。
また、マニュアル車であればギアパターンに不具合がないかどうかも項目です。
さらに、検査官は運転席にてクラクションマークやコーションラベルも確認します。
発煙筒(非常信号用具)は搭載されているかどうか、有効期限内かどうかもチェック項目となります。
スピードメーター検査
スピードメーター検査では、実際の車の速度とスピードメーターの表示に誤差がないかをチェックしています。
スピードメーターが40km/hになるまで車を加速させて検査場の計測器と比べてどの程度の誤差が出るかをチェックしています。
スピードメーター検査は、実際の速度と完全に一致しなければいけないわけではありません。
多少のずれが出るのは仕方がないので、誤差の許容範囲も10km/h程度に設定されています。
排出ガス検査
排出ガス検査は、マフラーから排出されるガスに含まれる一酸化炭素と炭化水素の濃度を計測します。これらは有毒ガスとされ、濃度が高すぎると環境汚染につながります。
排出ガス検査は、排気ガステスターを使用して実施する検査です。車をアイドリングにしてプローブと呼ばれる管状の装置を差し込みます。
整備不良やトラブルでエンジンの状態が悪いと排出ガスに影響します。また、走行距離が長くなるにつれて、この項目で不合格になるケースも発生します。
環境負荷が大きくなるだけでなく燃費の悪化の原因となっているかもしれません。
まとめ・社用車の車検は余裕を持って早めに申し込もう
車検制度は、定期的に変更があるため、社用車がある場合は事前に変更内容をチェックしておくことをおすすめします。
車検は車種によっても違うため、社用車が何台もあるようなケースでは、車検のタイミングや経費の処理などが煩雑になってしまうことがあります。
早めに車検のタイミングを把握してスケジュールを確認しておいてください。
創業手帳(冊子版)は、ビジネスに従事する様々な人に向けた記事を多数掲載しています。法律から日常のビジネスのいろはまで創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)