小さな会社が採用を成功させるには?現状の課題や採用活動でのポイントを解説
小さな会社でも採用活動を工夫すれば優秀な人材を確保できる!

商工中金が実施した「中小企業の人材確保に関する調査」では、企業規模別の採用人数を調査したところ、企業規模(年商)が小さな会社ほど新卒採用に苦労していることがわかっています。
特に、年商5億円以下の企業で新卒募集を行った企業のうち、過半数の企業が採用できていなかったことも判明しています。
小さな会社は大企業と比べて様々な課題や問題点があり、採用活動もうまくいかないケースが多いです。
しかし、採用活動を工夫することで小さな会社でも優秀な人材を確保できます。
そこで今回は、小さな会社の採用活動における課題や問題点から、成功させるためのポイントを解説します。
創業手帳では、小さい会社ほどおすすめの「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布中しています。採用だけに限らず、人材定着や労働環境整備、正社員化など雇用に関する助成金はたくさんあります。その中でも社労士が厳選したおすすめ助成金を掲載しています。初めての採用でもわかりやすく、支給額や助成率、スケジュールなどを整理していますので、ぜひこの機会にご活用ください。
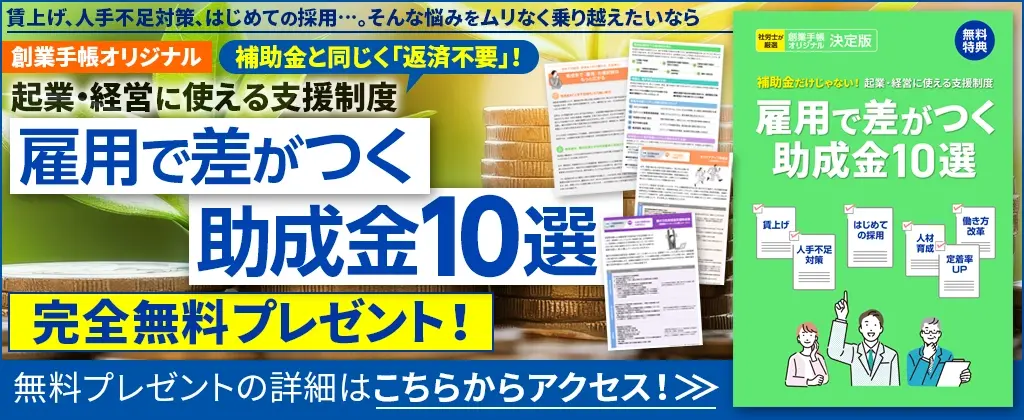
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
小さな会社の採用活動における課題・問題点

小さな会社は採用活動で苦戦を強いられることが多くあります。ここからは、小さな会社の採用活動における課題・問題点を紹介します。
売り手市場になっている
日本国内では年々少子高齢化が進み、労働力人口が減少しています。その影響で、採用市場は求職者よりも採用したい企業数のほうが多い「売り手市場」の状態です。
採用企業が多い買い手市場であれば、大手企業の選考に落ちた求職者が中小企業にも目を向け、応募するケースがみられました。
しかし、売り手市場では、小さな会社に目が向く前に大手企業の採用が決まってしまい、思うように採用できない中小企業が増えているのです。
知名度がない
大手企業に比べて小さな会社が不利になりやすい要因として、知名度の低さが挙げられます。
求人サイトに登録したとしても、知名度の低い会社はあまり目立たず、大手企業からの求人情報に注目されがちです。
また、求職者に自社の求人情報を見つけてもらえたとしても、企業に関する情報が少なければ、決め手が見つからず、別の企業に応募するケースもあります。
採用コストをかけられない
「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査 報告書」において、インターネットの求人情報サイトを利用した場合の1件あたりの平均採用コストは、28.5万円という結果が出ています。
小さな会社は大手企業に比べて採用コストをかけられません。そのため、求人広告や人材紹介などの高額なサービスを受けられず、採用難につながってしまいます。
また、小さな会社は、経営者や総務部などがほかの業務と並行して採用活動を進めているケースが多いです。
ほかの業務と並行していることで、問い合わせがあっても迅速に対応ができず、採用を逃してしまう場合もあります。
経営安定性や将来性で不安を持たれやすい
小さな会社は資金力が弱い傾向にあることから、求職者から経営の安定性や将来性を不安視される場合があります。
また、スキルアップやキャリア形成の面で不安に感じ、避けられてしまうこともあるかもしれません。
小さな会社は、求職者が不安に感じている部分も解消していく必要があります。
内定辞退が多い
新卒採用では内定辞退数が多いという課題もあります。特に4月~8月は大手企業に内定が決まったことが影響し、内定辞退が増える可能性は高いです。
しかし、問題となるのは、4月~8月ではない時期の辞退や、内定式後に辞退が発生したケースです。
このタイミングで内定辞退が頻繁に起きている場合は、会社側に何らかの課題がみられることが考えられます。
小さな会社が採用活動で意識したいアピールポイント

小さな会社が採用活動を行う際には、意識したいアピールポイントがあります。具体的にどのようなポイントを求職者に向けてアピールすべきか解説します。
事業の目標や将来の展望
自社が手掛ける事業の目標や将来の展望についてアピールすることは大切なことです。
歴史が長い会社であれば、自社の沿革や実績、現状などを中心にアピールしたくなるかもしれません。
しかし、将来性が見えなければ求職者は「長く働き続けられるか」がわからず、不安に感じてしまうものです。
また、自分が働いている姿を想像できず、応募までには至らないケースもあります。
単に事業の数値目標をアピールするのではなく、社員の雇用数をどれくらい増やしていきたいか、人材育成のプランなども発信していくことが大切です。
自社で働く強み・魅力
小さな会社であっても、大手企業にはない強みや魅力は見つかるはずです。自社の強みや魅力を求職者に対してアピールすることで、応募につながります。
近畿経済産業局が実施した「若者就職意識調査・企業フォローアップ調査」によると、学生が中小企業を希望する理由として、「雰囲気が良さそうだから」「自分の能力や強みが発揮できそうだから」「人間関係が良さそうだから」などの意見が多く挙げられています。
仕事の裁量や職場の雰囲気、人間関係などの面で魅力に感じられる部分をアピールすることが大切です。
仕事に対するやりがいや働く楽しさ
経営者側の意見だけでなく、実際に働く人が感じる仕事のやりがいや楽しさを伝えることもポイントです。
仕事に対するやりがいや働く楽しさが伝われば、求職者は仕事内容に対してイメージしやすくなり、興味・関心につながります。
なお、社員の声は従業員満足度調査によって収集することが可能です。
社員からやりがいに感じていることや、働く楽しさを集めることで、経営者だと気付けなかったやりがい・楽しさが見えてくるかもしれません。
キャリアパスやロールモデル
小さな会社であっても、今後どのようなキャリアパスを描けるのかを具体的にアピールできると、将来的な展望をイメージしやすくなり、応募につながる可能性があります。
キャリアパスを説明する際には、社員のロールモデルも取り入れるとよりイメージがつきやすくなります。
創業から間もない会社であれば、ロールモデルを紹介するのは難しいかもしれません。
しかし、管理職になるまでのスピードや業務を通して身につくスキル・経験などを紹介することで自社の魅力をアピールできます。
ワークライフバランス
東京商工会議所が実施した「2024年度新入社員意識調査」によると、就職先の会社を決める際に重視したこと(複数回答)として、「働き方改革、ワークライフバランス(年休取得状況、時間外労働の状況など)」を挙げた人は40.9%にも上っています。
意識調査を受けた約4割もの人が、就職先を決める上でワークライフバランスも重視していることがわかりました。
特に、現代の若者はワークライフバランスに重きを置いている傾向にあるため、仕事とプライベートのメリハリがつきやすいことや、福利厚生などを意識的にアピールしてみてください。
小さな会社が採用活動を成功させるためのポイント

小さな会社が採用活動を成功させるためには、以下のポイントも押さえておく必要があります。
求める人物像を明確にする
採用活動を始めるにあたって、「とにかく優秀な人材を採用したい」と考えていては、抽象的すぎてターゲットに合わせたアピールもできなくなってしまいます。
ターゲット層に適したアピールができるように、まずは求める人物像を明確にしてください。
求める人物像を設定することで訴求しやすくなるだけでなく、応募者とのミスマッチを防ぐことにもつながります。
企業のブランディング活動も進める
採用活動だけに注力するよりも、企業のブランディング活動も行うことが大切です。
小さな会社の採用活動の問題点として知名度の低さを挙げましたが、ブランディング活動を進めることで知名度が上がります。
自社サイトの作成やSNS・YouTubeを活用した情報発信なども、ブランディング活動として効果的です。
また、地方企業であれば、地域の経済紙やテレビ番組の取材に応じることでも知名度の向上につながります。
早い段階から就活生と接触する
小さな会社は、大手企業の内定出しがあらかた終わってから採用活動を開始しているケースも少なくありません。
しかし、これでは就活生と出会える数が減ってしまいます。また、同じ規模で早期から採用活動をしている企業にも就活生を奪われてしまう可能性が高いです。
このような状況に陥らないためにも、早い段階から求人活動を開始したり、就活生と接触する機会を積極的に設けたりしてみてください。
人事担当以外の社員にも協力してもらう
小さな会社が採用活動で成功するためには、人事担当以外の社員からも協力してもらう必要があります。
これまで採用活動に経営層が加わっていなかった場合は、経営層に積極的に関与してもらうよう相談することが大切です。
経営層が直接採用活動に携わっている会社は、経営陣と従業員の距離の近さが魅力的に感じられ、求職者からも興味・関心が集まります。
また、人事部以外の部署に協力してもらうことで、求職者は各部署の魅力を知り、仕事に対してイメージしやすくなります。
内定後に手厚いフォローを行う
新卒採用であれば、内定から入社までにかなりの期間がかかります。
そのため、内定者から仕事に対する不安や悩みが出やすかったり、就活を続けてより良い条件の会社に応募したりするケースも多いです。
こうした理由から、内定辞退につながる可能性もあります。内定辞退を防ぐためにも、内定後は学生を放置するのではなく、手厚くフォローすることが大切です。
仕事に対する不安や悩みを解消できるように、座談会や懇親会、面談を行ったり、入社前研修を実施したりすることがおすすめです。
小さな会社で取り入れたい採用手法

採用手法には様々な種類がありますが、小さな会社で取り入れたい採用手法をいくつか紹介します。
各手法にかかるコストの目安なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、求める人物像にマッチした人材に直接アプローチをかける採用手法です。
企業側から声をかけられるため、会社の知名度に関係なく認知してもらえます。
ただし、企業側から積極的にアプローチをかける必要があり、候補者を探してスカウトメールを送るなどの作業が必要です。
なお、ダイレクトリクルーティングのサービスを活用する場合、料金形態は成功報酬型と定額型の2つに分かれており、費用相場は異なります。
新卒採用のサービスを活用した場合、成功報酬型は1名につき30~40万円程度で、定額型では60~250万円程度が目安です。
リファラル採用制度
リファラル採用制度とは、自社の業務や社風などに詳しい社員が、友人・知人などの中からマッチする人材を探し、アプローチをかける採用手法です。
縁故採用と似ていますが、社員がマッチする人材を選定し、実際に採用できた場合は社員に対して報酬が支払われます。
リファラル採用制度でかかるコストは、紹介した社員に対して支払う報酬程度で、ほかのコストはほとんどかかりません。
なお、支払う報酬の目安は30万円未満が相場です。報酬金額を高く設定しすぎると、違法とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
SNS採用
企業のマーケティング活動としてSNSを運用するケースは多いですが、近年は採用活動の一環としてSNSを活用するケースも増えてきています。
知名度の低い小さな会社でも、SNS採用を取り入れることで求職者との接点を増やし、企業として存在感をアピールすることが可能です。
なお、SNSアカウントは無料で取得できるため、コストはほとんどかかりません。SNS広告を活用する場合でも、1円から予算を設定できるなど、低コストで運用できます。
資源が限られている中で効率的に採用活動を行いたい場合は、ぜひSNS採用を取り入れてみてください。
SNSでの採用を検討するなら「SNS運用ガイド」もあわせてご活用ください。業種別による相性がいいSNSなどを一覧化しています。無料でご利用いただけます。

就職・転職イベント
就職・転職イベントに参加することもひとつの方法です。イベントは、幅広い企業が一堂に会する総合型と、同じ業界内の企業が集結する業界特化型の2種類に分けられます。
就職・転職を具体的に決めていない人は総合型を選ぶ傾向にある一方、すでに特定の業界で働きたいことが決まっている人は業界特化型を選ぶ傾向です。
また、近年はオフラインだけでなく、オンライン上でイベントが開催されるケースもあります。
就職・転職イベントの参加費は各種イベントによって異なるものの、大規模な総合型かつ大手企業も数多く参加することから、小さな会社は不利になりやすいかもしれません。
一方、オンラインイベントであれば、求職者と接触する機会を増やしつつ、低コストに抑えやすいです。
オンラインで開催されている就職・転職イベントへの参加も検討してみてください。
OB・OG訪問
OB・OG訪問は、大学や同じ団体に所属していた先輩がいる企業を訪問し、面談を通して会社に対する疑問や不安を解消していく手法です。
就活生は実際にその会社で働く先輩社員から話を聞くことで入社後の姿をイメージできるため、ミスマッチを防ぎやすくなります。
また、OB・OG訪問はほかの採用手法と異なりコストはかかりません。
ただし、面談を受ける社員はその時間業務を中断することになるため、リソースをうまく分散させる必要があります。
インターンシップ
新卒採用を目指すなら、インターンシップを実施することもおすすめです。インターンシップを実施すれば、自社の認知度アップやミスマッチ防止などの効果が期待できます。
インターンシップにかかる費用は、主に内部コスト(学生に支払う交通費や給与(有給の場合)、採用担当者の人件費など)と外部コスト(求人掲載費用や人材紹介会社への成功報酬など)に分けられます。
コストの目安は、学生1人あたり20万円~40万円です。
企業の一般的な採用コストの相場が1人あたり70万円~90万円であることを考慮すると、採用につながるインターンシップの費用対効果は高いといえます。
まとめ・小さな会社は採用課題をクリアして優秀な人材を採用しよう!
小さな会社は、大手企業に比べて採用コストをかけられず、なかなか優秀な人材を採用できないと悩むことが多いかもしれません。
しかし、採用手法や求職者のニーズに合った魅力をアピールすることで、採用課題をクリアでき優秀な人材の確保にもつながります。
ぜひ自社の採用活動を一度見直し、今回紹介した採用手法やアピールポイントなどを取り入れてみてください。
採用コストがかけられない方へ「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布中しています。社労士おすすめの助成金で採用コストを下げましょう。詳しくは以下のバナーから。
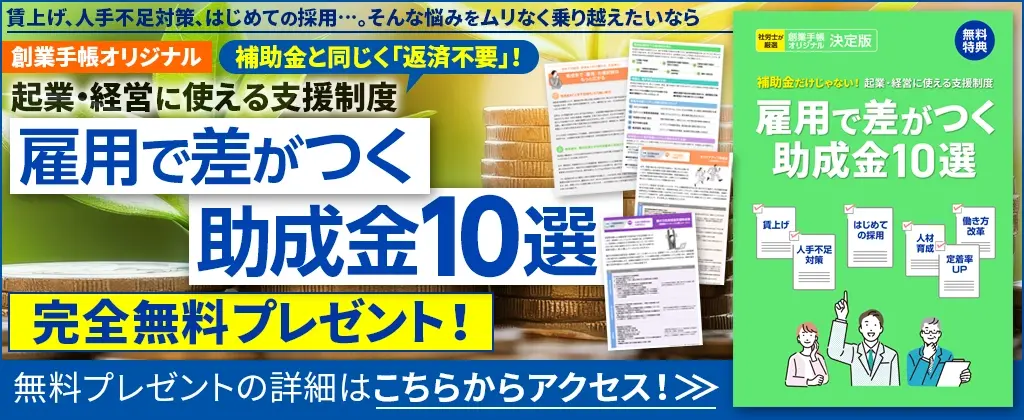
創業手帳(冊子版)は、創業・起業したばかりの会社でも役立つ採用活動や経営に関する情報を多数お届けしています。
企業規模を問わず使えるアイデア・最新情報なども提供しているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。




































