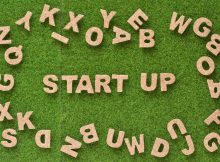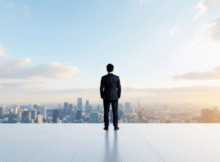副業容認はリスクがある?企業が押さえるべきポイントやメリットを解説
副業を容認する企業が増えている

近年、副業を容認する企業が増えています。
副業を容認すれば、社内だけでは得られないような知識やスキルを習得できるほか、人材を確保できるといった様々なメリットがあります。
しかし、情報漏洩や生産性の低下といったリスクを生み出す可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、なぜ副業を容認する企業が増えてきたのか、その背景を紹介すると共に、副業容認で企業が得られるメリットやリスク、準備すべきポイントや事例などを解説していきます。
副業の容認を検討している企業や企業が直面するメリットやリスクについて深く知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
副業を容認する企業が増加した背景

職業選択の自由が憲法で保証されているので、法律上副業は禁止されていません。
しかし、企業によっては就業規則で副業を禁止するほか、許可制が定められているケースもあります。
働き方改革が進む中、2018年に厚生労働省が作成した「モデル就業規則」の内容が変更されたことで、副業の解禁や容認する企業が増えてきました。
中でも、第11条にあった「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という項目が削除され、「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事できる」という副業や兼業に関する規定を新設したことが大きなポイントです。
なぜ、政府が副業を推進しているのか、その理由は下記が当てはまります。
-
- 希望する働き方を見つける環境づくりを提供するため
- イノベーションの創出のため
- 地方創生に活かすため
- 所得を増やすため
- 従業員のスキル向上のため
副業容認で企業が得られるメリット

政府も推奨している副業を容認することで得られるメリットについてみていきます。
社内では得られない知識・スキルを得られる
副業を容認すれば、従業員は社内では得られないような知識やスキルの取得を目指せるようになります。
自社内で従業員のスキルアップを図る場合、社内研修の実施や外部研修の受講といった方法が考えられます。
しかし、実施するためにはコストがかかるため、スキルアップする場の提供は簡単ではありません。
そのような中、副業を容認すれば従業員は自社内でコストをかけることなくスキルの習得が可能です。
副業が異業種であれば、これまでにないような視点で物事を捉えることにつながり、新しい知見を取り入れるきっかけにもなります。
斬新なアイデアを生み出す可能性もあるため、企業の成長にもつながります。
自律性・自主性の向上が期待できる
自律性や自主性を持った従業員が増えることも副業を容認するメリットの1つです。
グローバル化や労働力人口の減少、少子高齢化など、社会の変化が目まぐるしい中で大切なのは、自分でキャリアを開発する自律性や自主性です。
副業を容認して仕事の幅が広がれば、従業員には自分のキャリアに対する興味の高まりが期待できます。
従業員それぞれがキャリアについて主体的に考えてスキルアップを進めれば、生産性も高まるので企業の成長につながります。
企業イメージがアップする
「自由に働きたい」「縛られたくない」と考える人が多くなっているため、企業選びでは副業の容認や許可を挙げる人もいます。
副業をしたい人や柔軟な働き方を目指している人にとっては、副業を容認している企業には魅力を感じやすいです。
企業イメージを向上する場合、テレワークの導入や福利厚生の充実などの方法が考えられますが、副業の容認もイメージアップの方法としては有効的な手段です。
採用にもプラスに働く人材を確保できる可能性
副業を容認していることは企業の魅力の1つだといえます。そのため、新たな人材の獲得にも影響を与えます。
例えば、副業に挑戦したい人や副業に取り組んでいる人が転職をする場合、副業の解禁や容認しているかが企業選びの基準の1つです。
副業を希望する人材を広く受け入れられれば、人材確保の間口が大きく広がると予想できます。
また、自社が副業先として選ばれる可能性もあります。
あらゆる働き方が求められている現代において、正社員を希望する人以外にも、業務委託やアルバイトといった形態での働きを希望する人は多いです。
そういった人たちの受け入れを増やしていけば、優秀な人材の確保に役立つでしょう。
副業を容認するうえでの企業のリスク

副業の容認で、従業員のスキルアップや自律性向上が期待できます。しかし、一方でリスクが増えるといった注意点もあります。
副業容認によるリスクを十分に理解した上で、慎重に対応することが大切です。
情報漏洩が起きる可能性
副業容認で最も注意すべき点が情報漏洩です。
従業員が本業で得た知識のほか、営業情報や顧客データなどが副業先に漏れてしまったり、悪用されたりする危険性はゼロではありません。
例えば、自社に勤めている従業員が競合関係にある企業で副業することになった場合、自社で開発中の新商品に関する情報が他社に伝われば、市場での優位性を失ってしまいます。
顧客リストが流出してしまえば、個人情報保護法の抵触によって企業の信頼は低下してしまいます。損害賠償問題へと発展する恐れもあるため注意が必要です。
生産性の低下
副業を容認することで、生産性の低下につながる恐れもあります。
副業をする場合、本業の労働時間外で従事する必要があるため、休日や夜間といった時間帯で働くケースが多いです。
本来であれば休むはずの時間に仕事に取り組むため、十分に休息できずに疲れが溜まってしまう可能性があります。
その結果、本業での生産性低下につながるので注意が必要です。企業は従業員の副業状況を把握し、健康管理を怠らないよう伝えるといった工夫をする必要があります。
労働管理の複雑化
副業を容認すれば従業員の労働管理が複雑化するリスクもあります。企業では、自社での労働時間に加えて副業先の労働時間を含めた労働時間を管理する義務があります。
これは労働基準法第38条によって定められているため、徹底しなければいけません。
例えば、本業と副業を通算した労働時間が法定労働時間を超過する場合、企業は割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働が36協定で定めた上限を超えないように管理することも重要です。
仮に管理を怠ってしまえば従業員の健康を損なう可能性があり、生産性の低下だけではなく労災につながるケースもあるため注意してください。
社員の離職増加
副業を容認すれば企業イメージがアップし、採用にも良い影響を与える可能性が期待できますが、離職や独立を招く恐れもあります。
得た知識を発揮するためにも、独立をして新事業をスタートさせたり、副業先に専念したりするでしょう。
そのため、副業で得た知識やスキルを自社で発揮できる場を提供するほか、強みを活かせる仕事にアサインするなどの工夫が必要です。
自社に対して不利益となる行為を禁ずる旨を伝えることも検討してみてください。
副業を容認する前に企業が準備すべきポイント

いきなり副業を容認したとしても、準備不足によってトラブルにつながる恐れもあります。そこで、企業が副業を容認する際に準備すべきポイントを解説していきます。
社員の副業に対する希望を確認
まずは、従業員の希望を調査してください。副業を希望する人が社会的に増えているとはいわれていますが、自社ではいない可能性もあります。
そのため、自社ではどの程度の人たちが副業を希望しているのかを調査する必要があります。
希望人数だけではなく、どのような業種での副業を検討しているのか、期待する点や不安点など、実態を把握するためにも調査を実施してみてください。
副業容認の条件設定
副業を容認する上では、条件を設定する必要もあります。
その際には厚生労働省によるガイドラインを参考にして、副業をするための条件やルールなどを定めて社内で共有していきます。
副業を制限する場合についての条件も盛り込むことが大切です。
誓約書や副業申告書の活用
条件を設定したら、トラブルを回避するためにも誓約書や副業申請書の活用を検討してみてください。副業申告書には、以下の記載を求めます。
-
- 副業先の企業名称
- 所在地
- 業務内容
- 契約形態
- 労働時間、労働日数、労働期間 など
必要に応じて競業避止義務や秘密保持義務の記載や確認も必要です。誓約書では、コンプライアンス意識の向上や心理的な抑制効果が期待できます。
就業規則の見直し
副業でのリスク管理に備えて就業規則の見直しを図ることも重要です。
副業内容や労働時間の把握のためにも事前届出制の採用がおすすめです。報告や申告義務に対する規定を設ける際には、申告を怠らないようフォローする必要もあります。
また、副業の禁止や制限をする場合でも、その旨を就業規則に明記する必要があります。
競業避止規定を設ければ副業を容認したとしても、同業他社での副業を禁止したい場合に有効です。
ただし、就業規則を見直す際には従業員とのコミュニケーションも必要です。説明会の開催をするなどして双方が納得できる形を実現してください。
副業容認の周知
次に副業容認の周知です。何も報告せずに容認したとしても副業をスタートさせる従業員は少ないかもしれません。
就業規則の変更が終わった段階で説明会を開催すれば、新しい就業規則の内容を伝えるだけではなく副業容認を広めることができます。
その際には、副業を容認する理由についても解説し、副業に関する知識が少ない従業員向けに、セミナーや勉強会を開催するのもおすすめです。
労働時間の管理方法を検討
前述したように、副業を容認すれば従業員の過重労働を防ぐためにも労働管理が必要です。
従業員による自己申告や自己管理が現実的ですが、通算方法は定められていないので取り入れやすい方法を採用してみてください。
厚生労働省では「管理モデル」を提供しています。副業の労務管理の手続きの負担を軽くするためのもので、労働時間の上限設定や割増賃金の支払いといった2つの要素で構成されています。
労働基準法を守るためにも活用を検討してみてください。
副業を容認している企業の事例

最後に、副業を容認している企業の事例を紹介していきます。参考にするためにもチェックしてみてください。
メルカリ
フリマアプリを運営している株式会社メルカリでは、従業員の価値を最大限に発揮できるような労働環境や福利厚生を提供しており、その1つとして副業が推奨されています。
書籍の執筆やコンサルティングなど、幅広い業種の副業ができます。そのために有料セミナーを受講する際には費用が全額補助されるほか、ビジネス書を購入した際の費用も全額補助してくれます。
新しいチャレンジがしやすい環境が整っている企業です。
TOMOSHIBI
プロジェクト単位でメンバーを集められる仲間集めプラットフォームを運営するTOMOSHIBIでも副業を容認しています。
CEOを務める田中駆氏は、あるインタビューにおいて、「自分が使える時間やお金の中で挑戦できる限りすればいいし、その決定権は自分にある」と述べていました。
新しい働き方に対して柔軟な考えを持っている人物だと推測できます。
エンファクトリー
オンラインショッピング事業や専門家マッチング事業などを展開する株式会社エンファクトリーでは、人材理念として「専業禁止」を掲げています。
副業を必須としているわけではありませんが「パラレルワーク制度」を導入し、副業をすることで様々な気付きや機会を得られ、「自分はどこでもやっていける」という自信を身に付けることで、エンファクトリーを変革する力にもなると考えているようです。
実際に、本業とは別にWeb運用やライター、犬用のグッズ販売、Webプランナーなど、様々な副業をしている従業員が在籍しています。
まとめ・リスクを考慮したうえで副業を容認しよう
働き方改革が今後さらに進んでいけば、副業を希望する人がより増加し、重要性が高まることが考えられます。
従業員のスキルアップや自律性の向上、企業のイメージアップなど、様々なメリットが得られ、人材採用にも良い影響を与えると予想できます。
しかし、情報漏洩の危険性や就業規則の見直しが必要になるなど、リスクもあるため注意が必要です。
企業はメリットだけではなくリスクを踏まえた上で副業の容認を検討してみてください。
副業容認は、企業にとって就業規則や制度設計の見直しが欠かせません。
「創業手帳」では、人事・労務に関するヒントも満載です。無料でお配りしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)