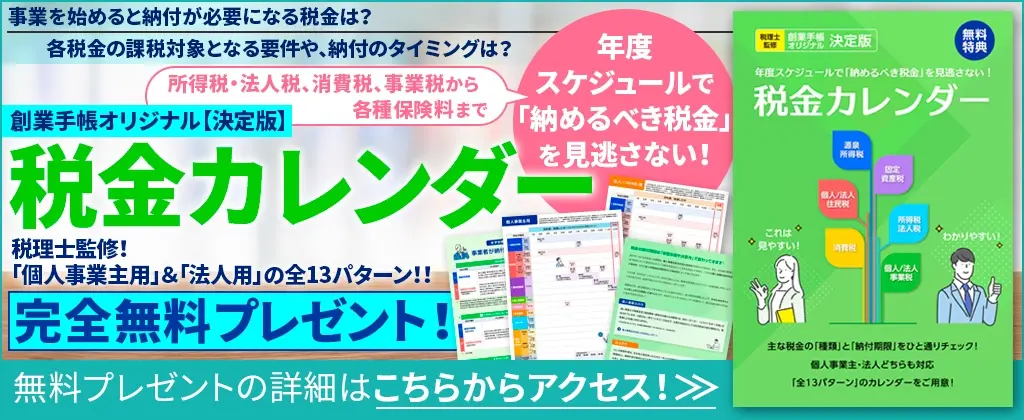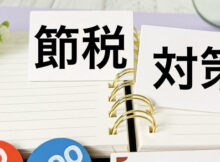一人親方の労災保険料は経費計上できる?計上時のポイントなどを解説
一人親方の労災保険について理解し、節税に役立てよう

建設業界では、個人で仕事を請け負っている事業主のことを「一人親方」と呼んでいます。
一人親方として活動している人、もしくはこれから一人親方として活躍したいと考えている人の中には、労災保険に加入する際に保険料を経費として計上できるのか気になっているかもしれません。
結論からいえば、一人親方は労災保険料を経費として計上することはできないこととなっています。今回は、一人親方の労災保険と経費計上について詳しく解説していきます。
創業手帳では、「経費削減の具体例を知りたい!」「経費って節税につながるの?」と思われている方に『経費で損しないためのチェックシート』をご用意しました。無料でお使いいただけますのでぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
一人親方は労災保険に加入できる?

そもそも一人親方は労災保険に加入できるのでしょうか。結論として、原則一人親方は労災保険に加入することができません。
なぜなら、労災保険というのは企業に雇用されている労働者のための保険制度であり、一人親方は個人で事業を請け負っていることから、対象に含まれないのです。
ただし、一人親方は特例で労災保険に加入することができます。特例を使って加入はできるものの、経費として計上することはできません。
ただし、労災保険の内訳によっては経費計上できる費用もあります。通常の労災保険の加入とは異なることも多いため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
労災保険の特別加入とは
労災保険の対象は企業に雇用されている労働者に限られますが、特別加入を利用すれば従業員を雇用していない一人親方でも加入することが可能です。
また、労働者を雇用していたとしても、労働者の使用日数が1年で合計100日に満たない場合、一人親方として加入できます。
労災保険の特別加入が可能な事業は以下のとおりです。
-
- 自動車を使って旅客または貨物を運送する事業、または原動機付自転車・自転車を使って貨物を運送する事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)
- 土木・建築その他の工作物の建設や改造、修理など、もしくは解体やその準備を行う事業(大工・左官・とび職人など)
- 漁船による水産動植物を採捕する事業
- 林業
- 医薬品の配置販売を行う事業
- 再生利用を目的とする廃棄物の収集から運搬、選別、解体までの事業
- 船員が実施する事業
- 柔道整復師が実施する事業
- 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する「創業支援等措置」に基づいた、同項第1号に規定する委託契約・その他契約に基づき、高年齢者が新たに開始する事業または同項第2号に規定する、社会貢献事業にかかる委託契約・その他契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などが行う事業
- 歯科技工士が行う事業
- 特定フリーランス事業(企業や消費者から業務委託を受けて行う事業)
一人親方が労災保険で経費計上できる費用の内訳
一人親方は特別加入を利用して労災保険に加入することはできるものの、原則経費として保険料全額を計上することはできません。
しかし、所属する団体に支払う費用については経費計上が可能です。経費計上が可能な費用の内訳は、以下のとおりです。
入会金
入会金は、一人親方の団体へ入会する際に支払う金額です。入会金の支払いは基本的に入会時の1回だけに限られ、金額は各団体によって異なります。
組合費
組合費とは、一人親方団体の運営に必要な費用として使われる金額です。組合費も入会金と同様に、各団体で支払う金額が異なります。
ただし、費用に関しては毎月分を納付する必要があります。
その他の諸会費
入会金や組合費以外に、各団体によってはその他の諸会費を支払うことになる場合もあります。
例えば更新手続き時に発生する更新手数料や、労災事故を起こした場合の手続き費用、労災保険から退会する際の手続き費用、組合員証を再発行する際の手数料などです。
これらの費用がすべてかかるところもあれば、手数料なしで対応してくれる団体もあります。
一人親方が労災保険料を経費計上する際の仕訳方法

一人親方が自分のために支払った労災保険料の経費計上は認められていません。
しかし、上記で紹介した一人親方団体への入会金や組合費、その他の諸会費などは経費計上が可能です。
では、実際に経費計上する場合、どのように仕訳を行えば良いのでしょうか。それぞれのケース別に仕訳方法を解説します。
自分の労働保険料を支払ったケース
自分の労働保険料を支払った場合、経費計上は認められていないため、帳簿への記帳は不要となります。
ただし、事業用口座から労働保険料を出した場合、借方の勘定科目を「事業主貸」にすることで仕訳することは可能です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 事業主貸 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 | 労働保険料 |
事業用口座から出した場合でも、上記のように仕訳を行えば事業主個人の支出として処理できます。
雇用している従業員の労働保険料を支払ったケース
一人親方でも労働者を雇用している場合、労働者のために支払った保険料は「法定福利費」として計上できます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 法定福利費 | 30,000 | 現金 | 30,000 | 労働保険料 |
また、労働者が負担する労働保険料を事業主で一時的に立て替えた場合、「立替金」として計上することも可能です。立替金を活用した場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 法定福利費 | 30,000 | 現金 | 30,000 | 労働保険料 |
| 立替金 | 15,000 | 労働保険料労働者負担分 |
労災保険の入会金などを支払ったケース
一人親方が労災保険に加入する際には、一人親方の団体に入会することになります。
この入会時に発生した入会金や組合費、その他の諸会費は経費として計上することが可能です。
これらの費用を経費として計上したい場合、勘定科目は「諸会費」や「雑費」、「支払手数料」などに当てはまります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 諸会費 | 1,000 | 現金 | 1,000 | 労災入会金 |
労災保険の加入方法

一人親方が労災保険に加入する場合、どのような手続きをとれば良いのかわからない人もいるでしょう。そこで、ここからは労災保険の加入方法について紹介します。
1.特別加入団体を立ち上げて申請する方法
新たに特別加入団体を立ち上げて、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長経由で、都道府県労働局長に申請書を提出し、承認を受ければ特別加入が認められます。
特別加入団体として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-
- 一人親方などの相当数を構成員とする単一団体である
- その団体が法人かどうかは問わないが、構成員の範囲や地位の得喪の手続きなどが明確、またその他団体の組織や運営方法などが整備されている
- 団体の定款などに規定された事業内容からみて、労働保険事務の処理が可能
- 団体の事務体制や財務内容などからみて、労働保険事務を確実に処理する能力があると認められる
- 団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、各地域に相当する区域を超えていない
特別加入申請書には特別加入を希望する人の業務内容や業歴、希望する給付基礎日額などを記入します。
申請書は厚生労働省のホームページからダウンロードで入手することも可能です。
また、申請書を提出する際には、以下の書類も添付する必要があるため、事前に準備をしておきましょう。
-
- 一人親方などの団体における定款や規約などの目的、組織、運営などを明らかにする書類
- 業務災害の防止について、一人親方などの団体が講ずるべき措置および守るべき事項を定めた書類
2.特別加入団体に認められている組合に加入して申請する方法
もうひとつの方法は、すでに特別加入団体として認められている組合に加入し、その団体を通じて特別加入をする方法です。
一人親方はまず特別加入団体に加入の申し込みを行い、入会金などを支払って加入します。
特別加入団体は一人親方の加入を認めたら、特別加入に関する変更届を作成し、監督署長を経由して労働局長に提出することになっています。
例えば、新たに一人親方が加入した際には、変更届の「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」の欄に必要な事項を記入して提出してください。
特別加入で健康診断が必要となるケース
特別加入を希望する場合、特定の業務に一定期間以上携わっている人は申請時に健康診断を受けることになります。
健康診断が必要となる業務の種類と従事した期間、必要な健康診断は以下のとおりです。
| 業務内容 | 業務に従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
| 粉塵作業を担う業務 | 3年以上 | 塵肺健康診断 |
| 振動工具を使用する業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断を実施した結果、すでに疾病があり療養に専念しなくてはならないと認められた場合、従事する業務内容に関わらず特別加入が認められない場合もあります。
また、特定の業務から転換が必要と認められた場合、当該業務だと特別加入は認められませんが、それ以外の業務であれば特別加入が認められます。
一人親方の労災保険料は社会保険料控除の対象に含まれる
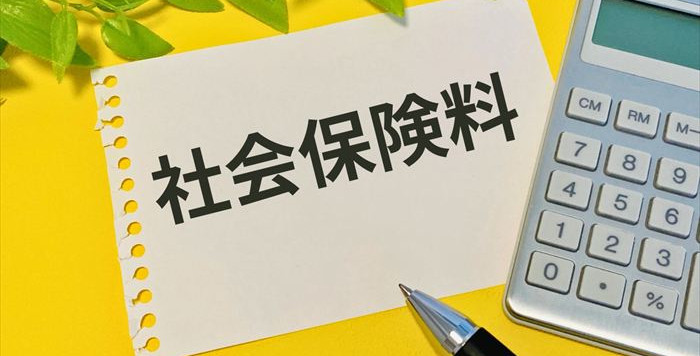
一人親方の労災保険料は経費として計上できないものの、その代わりに「社会保険料控除」の対象に含まれます。
ここで、労災保険料と社会保険料控除の関係について詳しく解説します。
確定申告の「社会保険料控除」に記入する
一人親方が特別加入して支払った労災保険料は、社会保険料控除にできます。
社会保険料控除は1月1日から12月31日までの1年間に支払った社会保険料を控除する、所得控除のひとつです。
社会保険料控除を活用することで、所得税や住民税を計算する際の所得金額から社会保険料として支払った金額を控除でき、税金の負担を抑えられます。
確定申告に記入する際には、第一表の「所得から差し引かれる金額」にある「社会保険料控除(13)」の欄に支払った保険料の合計額を、確定申告の第二表「(13)社会保険料控除(14)小規模企業共済等掛金控除」の欄に支払った保険料の種類と金額の内訳を記載します。
確定申告に社会保険料控除について記入しないと控除が受けられず、税金の負担が軽減されないので書き忘れないように注意してください。
労災保険以外で控除の対象になるもの
一人親方で社会保険料控除の対象に含まれるのは、労災保険だけではありません。国民健康保険料や国民年金保険料も、控除の対象になります。
国民健康保険料は、一人親方を含む個人事業主は原則全員が加入しているもので、所得や加入者数、年齢、地域、介護の有無などに合わせて納める保険料が異なります。
国民年金保険料は、一人親方も含めて会社に所属していない人全員が加入する年金制度で、所得に関わらず一定の金額を支払わなければなりません。
保険料は2年前納制度もあるため翌年度分も公表されており、令和7年度は17,510円、令和8年度は17,920円と発表されています。
社会保険料控除を受けるためにはどの社会保険料に対していくら支払ったか申告する必要があり、保険の種類によって控除証明書の添付が必要です。
国民年金保険料については控除証明書の添付が必要となりますが、国民健康保険料だと証明書は不要になります。
まとめ・一人親方は労災保険を経費計上できないが、社会保険料控除として活用できる!
一人親方は原則労災保険に加入できないものの、特別加入の制度を活用すれば加入することができます。
労災保険料自体の経費計上は認められていませんが、特別加入団体に支払った入会金や組合費、その他諸会費などは経費として計上することが可能です。
また、労災保険料は経費計上できないものの、社会保険料控除として活用することができます。
社会保険料控除を受けたい場合は確定申告に記入する必要があるため、忘れずに申告するようにしてください。
創業手帳(冊子版)は、その他にもすぐに取り組める節税対策を掲載しています。税金の知識は知っているか知っていないかで数十万円支払額で変わってくるケースもあります。そこで「税金チェックシート」や「税金カレンダー」を用意しましたので、事業主が知っておくべき税金について解説しているので、あわせてご活用ください。無料でご利用いただけます。
(編集:創業手帳編集部)