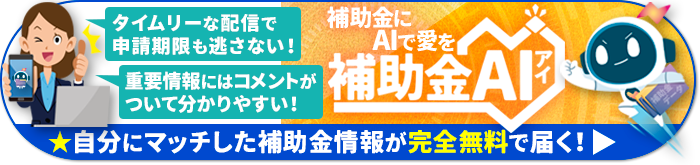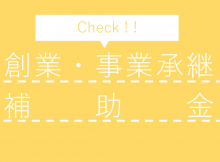補助金をもらっても返金になる?!知らなかったでは済まされないNG行動と対策
補助金は“もらって終わり”ではない──採択後こそ注意が必要

助成金には返済義務はないため、もらって終わりと感じてしまうかもしれません。しかし、受給後の管理を怠れば返金が求められるケースがあります。
補助金は、採択されてからも経費管理や報告書提出など多くの義務が課されます。もしも提出漏れやルール違反があれば補助金を返金しなければいけません。
さらに次回申請不可などの不利益が生じるリスクもあります。
本記事では採択後に発生するNG行動とその具体的な防止策を事例を交えて解説します。
補助金を正しく活用するためには、制度ごとのルールや運用上の注意点を理解しておくことが大切です。
創業手帳の『補助金ガイド』では、主要な補助金・助成金の最新情報に加え、申請時・採択後の注意点まで丁寧に解説しています。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
えっ、返金しなきゃいけないの!?補助金の“落とし穴”とは

補助金は、一定の要件を満たした場合に申請して審査を通過すれば地方自治体や団体から金銭を受給できる制度です。
「新しい事業のスタートを応援したい」、「地域の活性化を目指したい」といったそれぞれの団体の理念に基づいた制度であり、補助金によって目的は違います。
補助金を申請する企業側は、補助金を活用することによって設備投資や人材補充が可能になり事業の幅が広がります。
しかし、企業が交付された補助金は返金しないでいいお金と思い込んでいると落とし穴にはまってしまうかもしれません。補助金の返金について知っておきましょう。
補助金は「もらって終わり」ではない
補助金は一度受給できれば返す必要がない分、融資よりも利用しやすいと感じる人もいるかもしれません。
しかし、補助金の受給後にも書類の提出や報告といった義務があり、実地調査を求められるケースもあります。
実績報告や帳簿保存などの義務には、適切に管理対応しなければ返金対象担ってしまいます。
さらに書類では問題なくても提出した事業計画通りに実施していないと返金を求められたり、次回申請への影響が生じたりする可能性もあるかもしれません。
補助金は、採択直後から報告期限までの全スケジュールを通じて期限とルール遵守の行動を取らなければいけません。
義務やルールを見落とすと返還リスクがある
補助金を受給してからの返還するように求められる条件は、その補助金ごとに定められています。
しかし、国から国以外への団体へ支給する補助金全般については「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に定めがあります。
まず、補助金を別の目的に使用するといった受給時の条件に違反するような行動は許されません。
受けた補助金を、承認を受けずに譲渡、交換、貸付、担保に供することも禁じられています。
申告した目的通りに補助金を使用していないければ、その補助金制度の目的を達成できません。よって後から調査などで不正が判明した時には、補助金の返還を求められます。
補助金にありがちなNG行動1|証憑書類の不備や保存漏れ

補助金は、安易に申請してしまうと後から負担の多さに驚くかもしれません。特に書類の提出や保存に関しては厳しいルールが設定されています。
どういった行動がNGになるのか紹介します。
経費の支払い証明が不十分(領収書・振込明細など)
補助金の交付が決定して事業を開始した時に徹底してほしいのが経費の管理です。
補助金に関わる事業は必ず計画通りに実施する必要があるほか、経費については支払いを証明する書類をすべて保存、管理しなければいけません。
もしも証憑が不足すると経費として認定されず、返還を命じられるリスクがあります。
経費を証明する書類にはいろいろありますが、具体的には以下のものが当てはまります。
-
- 見積書
- 契約書
- 発注書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 銀行振込の控え など
金額がわかるクレジット明細だけでは経費証明が不十分です。
経費の支払いがある時には、すべての必要書類を揃えて分類して保存するようにシステム化します。
後の実績報告でも経費に関わる情報は必要なので何に使った経費なのかわかるように記録を残してください。
実績報告書に必要な添付資料が欠けている
実績報告書には添付資料を求められることがあります。報告書に必要な資料が欠けていると受理されず、返金リスクや事務指導を受けることもあります。
また、金銭の受け渡しに直接関係しなくても写真や納品書で記録することも大切です。これらの情報が不足すると経費裏付けが不十分となり、認定されないことがあります。
書類は社内で提出前にチェックリストで資料漏れを確認するなど、不備を防ぐための体制を整えてください。
電子保存ルールの未確認・経理処理のミス
補助金の交付を受ける時には、書類や経理処理のルールの見直しも求められます。
具体的には、電子帳簿保存法において、電子取引データを紙に印刷して保存することは原則禁止です。
法が定める「真実性」や「可視性」の要件を満たさない保存をしていると証憑として認められず、補助金の返金対象になる可能性があります。
電子データは、紙とは違ってデータ破損や削除してしまうリスクも考えなければいけません。定期的なバックアップなどの社内ルールも必要になります。
紙から電子に移行することで経理処理も変わります。会計ソフトを活用すればデータの記録と保存期限の管理を効率化可能です。
経理処理のミスを防いで確実に守る体制を構築してください。
補助金にありがちなNG行動2|対象外の経費を使ってしまう
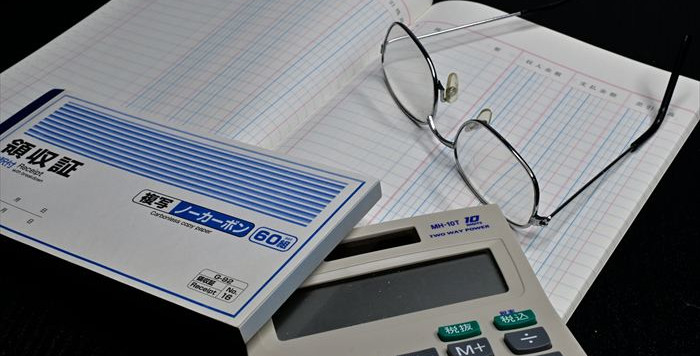
補助金申請をする時に気になるのが、そもそもその経費が補助対象になるかどうかです。
補助金によって補助対象経費は違うため、必ず何の経費が対象になるのか確認してから申請してください。
補助対象にならない支出を含めてしまう(例:中古品、税金、人件費)
補助金の申請において対象外経費を計上すると不認定となり、返金を求められる可能性が非常に高くなります。
補助金には、その目的に応じて「この費用であれば補助します」という補助対象経費の範囲が設定されています。
例えばIT導入補助金の通常枠なら事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入支援、セキュリティ対策推進であればサイバーインシデントに関するリスクを低減するシステムに対しての補助などです。
補助対象が設定されている補助金に対して税金や中古品、人件費といった対象にならない支出は含められません。
事前に対象可否を確認して、対象外の経費は申請内容から必ず除外する必要があります。
経費の報告をする時にも、経費区分を明確化して誤申請や返金リスクを防ぐ管理が大切です。
目的外の用途に流用してしまう
補助金が手元に入ると金銭に余裕があるからと、目的以外の支出に使ってしまうことがあります。
しかし、補助金を本来の目的以外に使うと不正使用とみなされ、返還命令を受ける場合があります。
もしも補助金の用途変更を希望する時でも事前承認が必要です。絶対に自己判断で補助金を流用してはいけません。
少額の変更でも必ず事務局に相談し、適正な使用か確認するようにしてください。
補助対象経費の定義をあいまいに理解している
そもそも対象経費の定義を誤解していたり、あいまいな理解のままでいたりするケースもあります。
補助対象経費の定義を理解していないと申請や計上で誤りとなり、返金リスクが高まります。
補助金の対象経費や区分は公募要領や説明会で必ず確認してください。疑問点は放置するのではなく、事務局や専門家に確認して早期に解消したほうが良いでしょう。
補助金にありがちなNG行動3|「事後申請OK」と誤解してスタートする
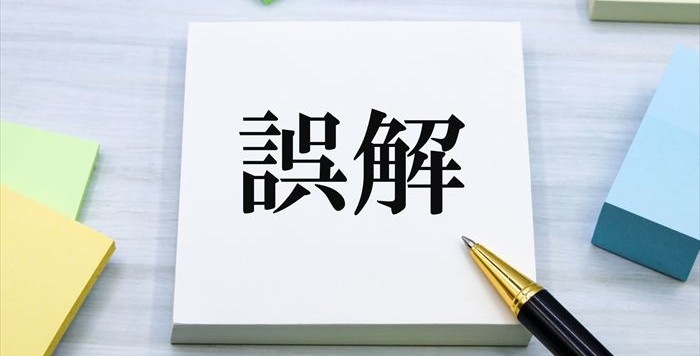
補助金は、スケジュール管理に厳しく、申請や実施の順番は遵守しなければいけません。
「結果は同じだから先に購入した」といった軽率な行動もリスクになります。どういった行動がNGになるのか確認してください。
「もう購入してしまった」「契約済みだった」ために申請が通らない
補助金は後払いで支払われます。補助金を前払いでもらえるものと誤解する人もいますが、契約や支出を先に行うと原則として補助対象外です。
交付決定通知後に事業に取組むという順序は守らなければいけません。事前に支出した費用は全額自己負担になってしまうケースもあります。
「もう購入した設備を補助対象にしたい」と考える人もいるかもしれません。
しかし、補助金は後付け申請は認められないので購入や契約を含めた手続きを適切な順番で実施してください。
補助金は“交付決定後”の支出しか認められないのが原則
補助金は、交付決定後の支出しか認められず、交付決定前の支出は補助対象外となるのが原則です。
一部例外がある場合であっても事前承認が必要で、自己判断で事前に支出すると交付が認められなくなります。
補助金を申請すると決めた時点でスケジュールを管理して、順序を間違えないようにしてください。
補助金にありがちなNG行動4|導入したツール類の解約

補助金を受け取って、会計ツールやソフトウェアを導入したいと考える事業者も多いはずです。
しかし、ツールの導入は慎重に進めないと補助金を返還しなければいけなくなるかもしれません。
導入したツールを解約してしまうと返還に
補助対象の経費は、その区分と期間を確認してください。補助対象の期間とは、補助金の適用対象になる期間であり数年にわたるケースもあります。
この補助対象期間に補助金で導入したツールを解約すれば補助金の返還を求められます。
導入したツールを解約したい場合には、別途手続きが必要なので補助金の窓口に問い合わせてください。
購入したツールを売却して誤魔化してしまう
補助金を使って買い切りのツールやソフトを購入した場合、補助対象期間に売却すれば補助金の返還を求められます。
「こっそり売ってもばれない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、補助金交付ごとの報告書類には、ツールの使用状況がわかる書類やスクリーンキャプチャが求められることがあります。
補助金の手続きについて虚偽の報告をすれば罰金などのペナルティを受けることもあるので虚偽の報告は絶対に避けてください。
補助金は「もらって終わり」ではない──報告義務の重要性

補助金は、交付を受けて終わりではありません。補助金の目的を達成するためには、交付を受けた団体、事業者は適切に補助金を活用する必要があります。
どのように活用されているかを知るために重要となるのが報告です。ここでは、どういった報告が必要になるのかをまとめました。
実績報告・完了報告の書類提出が必要
補助金の対象となる支出や事業が終了後は、成果や経費を証明する実績報告書を期限内に提出します。
あらかじめ期限が定められており、報告の遅延や不備があれば返金や次回申請への影響を招くかもしれません。
実績報告と完了報告は所定の様式や添付書類が公募要領に記載されています。必要書類や様式を事前に確認し、余裕を持って作成するようにしてください。
数年間の帳簿保存や事業実施報告が求められることも
補助金に関わる帳簿や契約書などは制度により3~5年間の帳簿保存義務が課される場合があります。
この保存期間中に実地調査や追加報告を求められることもあるので、定期的に確認できるように保存しなければいけません。
多くの補助金では、報告事項の様式や項目が同じなので提出した報告書類を保存しておけば翌年度以降の報告に活用可能です。
書類や帳簿の保存義務は数年にわたるため、担当者が変わる可能性もあります。
補助金に関わる書類や帳簿を社内で継続的に管理できるような仕組みを構築してください。
安心して補助金を活用するための3つの心得

補助金の内容は魅力的であっても、返金のリスクが気になる人もいるはずです。ここでは安心して補助金を活用するための心得をまとめました。
①公募要領・手引きは必ず目を通す(読み飛ばさない)
補助金を申請、交付を受けるための基本として公募要領や手引きは必ず目を通します。
制度条件や対象経費は公募要領に詳細が記載されているので、対象となるのか、どれだけの補助が受けられるかチェックしてください。
面倒に感じるかもしれませんが、うっかり読み飛ばして期限違反や対象外経費計上をしてしまうケースがあります。
複数人で確認して重要箇所は印刷してマーカーを引くようにしてください。難しい場合には、専門家と協力して取組みましょう。
②スケジュール・申請プロセスを逆算して行動する
補助金は、申請プロセスとスケジュールが厳密に定められています。事業開始日から逆算して申請期間や審査期間を計画しなければいけません。
複数の手続きを並行するような場合は、それぞれのスケジュールを把握して余裕のある日程を確保します。
ひとりで担当するとミスに気づかないケースが多いので、期限や納期はカレンダーや共有ツールで管理するようにおすすめします。
③支援機関・専門家に相談しながら進める
補助金の申請は、使用されている用語に耳なじみも少なく、社内の人材では手続きが難しいかもしれません。
社内リソースに限界がある時には、補助金申請支援の専門家へ相談しながら進めれば、制度理解の誤りや不備を予防可能です。
補助金申請支援の経験がある専門家であれば、経費区分や書類作成について高い精度でチェックしてくれます。
申請前から報告まで継続して適切にサポートしてくれる支援機関もあるので積極的に活用してください。
④「採択後の流れ」まで見据えて体制を整えておく
補助金は、採択されてからの業務や保存義務について担当者と共有し、役割を明確化してください。
支出関連の報告は多いので、会計部門と連携して証憑や帳簿管理の体制を整えます。
報告に関して不備や期限超過のリスクを最小化するには、外部から継続的に支援を受けることも検討してください。
まとめ:準備不足は命取り。補助金は「ルールを守って活用」しよう
補助金の交付を受ける時には、報告や書類保存といった義務もあります。申請者は採択されてからも、義務や返金リスクがあることを理解しなければいけません。
準備や報告を怠ればペナルティにつながるリスクがある一方で、適切に補助金を使えば事業拡大や資金繰り安定に直結し、次回申請の可能性も広がります。
支援機関を活用して不明点を事前に解消し、将来につながる補助金の活用を目指してください。
補助金は企業を支援する心強い制度ですが、対応を誤れば返金や次回申請不可といったリスクもあります。
そうした失敗を防ぐためにも、最新の情報と正しい手続きを常に確認することが重要です。創業手帳の『補助金ガイド』では、主要な補助金のポイントや注意事項をまとめています。リスクを避け、確実に成果につなげたい方は、ぜひご覧ください。

(編集:創業手帳編集部)