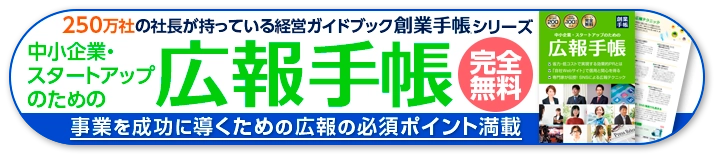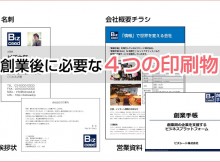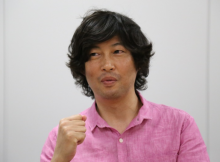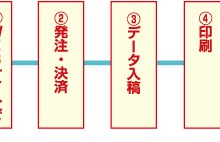ZINEとは?作り方や費用相場、販売方法まで徹底解説!
デジタル時代に注目を集めるZINE
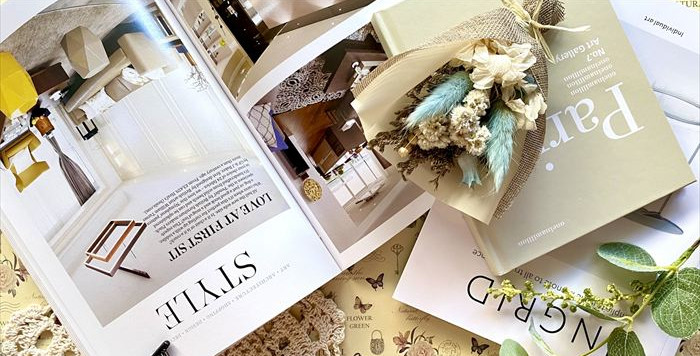
スマートフォンやインターネットが普及するデジタル時代の中で、アナログの「ZINE(ジン)」が注目を集めています。
ZINEは雑誌(magazine)の一部を意味する言葉で、写真やイラスト、エッセイ、詩などを自由にまとめて作る小冊子です。
しかし、いざ自分で作ろうと思うと、「どのような手順で作ればいいの?」「費用はどのくらいかかる?」「販売するにはどうすればいい?」といった疑問も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ZINEの基本から作り方、印刷や費用相場、販売方法までをわかりやすく解説します。これからZINE制作に挑戦してみたい方はぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
ZINE(ジン)とは?
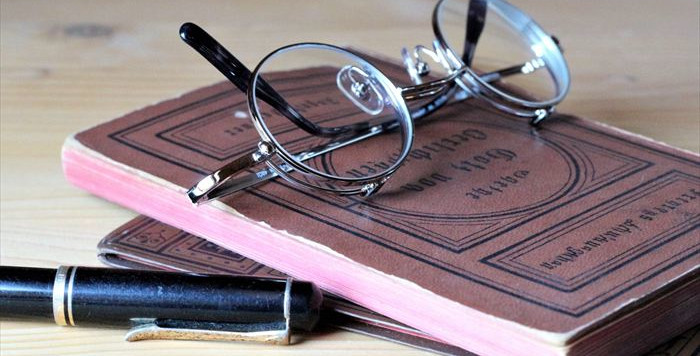
ZINEとは、個人や少人数で制作した自主制作による出版物を指します。一般的に書籍を出版するとなると、特定の出版社や編集者を通すことになります。
出版社や編集者を通してしまうと売れる本にするために、自分のアイデアがそのまま採用されないケースがほとんどです。
しかし、ZINEは自主制作で作ることになるため、自分が思い描きたいものやアイデアをそのまま表現できます。
ZINEの歴史
ZINEはもともと1930年代に作られたファン雑誌(fanzine)が起源とされています。
当時、SFファンの間で非営利の出版物を自分たちで制作し、持論やアイデア、映画・雑誌などに対する感想などを記し、交換し合う文化がありました。
その後、1950年代に入るとアメリカの詩人たちがオリジナル詩集を制作しはじめ、さらに1960~1970年代ではアメリカやイギリスなどでパンクカルチャーやサブカル文化の一部としてZINEが広まり、日本にも浸透していきます。
2000年代以降はインターネットやPCの普及にともない、個人でもZINEを簡単に制作できるようになりました。
同人誌との違い
ZINEはよく同人誌と混同されることが多いです。多くの共通点があり、明確に異なるといえる部分がないためです。
しかし、傾向として同人誌はある特定のジャンルや作品に対するファン活動の一環として制作され、ZINEはより自由なテーマと表現によって個人の視点を描くことが重視されています。
いずれも表現する際の形式は自由なので、制作者がどちらで名乗るか、どこで発表するかによって変わってきます。
ZINEを制作するメリット

デジタル時代に注目を集めるZINEにはどのような魅力があり、制作する人が増えているのでしょうか。ここでは、ZINEの魅力とメリットを解説します。
自分の思い通りに表現できる
ZINEを制作する最大のメリットとして、自分の思い通りに表現できる点が挙げられます。
テーマを決めるところから制作、配布・販売に至るまで、すべての工程を自分で担うことになります。
一般的に本を作ろうとすると、出版社やスポンサーなどの意向も取り入れなくてはなりません。
しかし、ZINEならそのようなしがらみが一切なく、自分が「こう作りたい」と思ったものをそのまま表現できます。
また、売れることを目的に本を作ろうとすると、誰でも共感するようなテーマなどを採用する必要があります。
しかし、ZINEであれば一部の人にしか刺さらないニッチなテーマを選ぶことも可能です。
誰でも手軽に作れる
ZINEは誰でも手軽に作れるというのも、1つのメリットです。出版社から本を出したくても簡単に出せるものではありません。
ZINEの場合はページ数が少ないものも多く、思い立った日に制作に取りかかり、数日で完成させてしまうことも可能です。
新たな交流やコミュニティ形成につながる
ZINEは同じ趣味を持つ人との交流を深め、コミュニティの形成にも役立ちます。
ZINEを販売するイベントに参加すれば、テーマについて共通の趣味を持つ人と知り合うことができ、そこから作品の交換会や一緒に展示会を開催することも可能です。
また、同じ趣味を持つ人だけでなく、同年代や同郷、同じ職業の人などで新たな交流が生まれることもあります。
希少性が上がる可能性もある
本を出版する際、「一度に大量の本を印刷・製本しなくてはいけない」「売れなかったら在庫として抱えることになる」と不安に感じる人もいますが、ZINEは1冊からでも制作することが可能です。
自分用として1冊だけ作ったり、友達に配布する分だけ印刷したりすることもできます。
このように、少部数で作られることがほとんどなので、突然人気が出るとすぐに売り切れてしまい、二度と手に入らなくなる場合もあります。
その結果、ZINEの希少性が高まるかもしれません。
プロモーションとして活用できる
ZINEをプロモーション活動の一環として活用することもできます。
例えば、自作のアクセサリーをアピールするために、これまでに手がけた作品の写真集を出したり、イラストレーターが自分の作品を1冊にまとめたりすることも可能です。
また、アーティストがプロモーションとブランディングを兼ねて、自分で制作したZINEをイベントなどで配布するケースもみられます。
自分の世界観を思い通りに表現できるからこそ、プロモーションやブランディングにも活用しやすいです。
ZINE制作の費用相場

ZINEを制作しようと検討している人の中には、「どれくらいの費用がかかるのか気になる」という人も多かもしれません。
ZINE制作にかかる費用は、印刷・製本などもすべて自分で行う場合と、小ロットの印刷にも対応してくれる印刷業者に依頼する場合で異なります。
すべて自分で行う場合、1部あたりの印刷費用は160円~800円程度で収まります。一方、印刷業者に依頼した場合は1部あたり500円~800円程度です。
すべてモノクロで印刷する場合は価格を抑えられますが、写真集・イラスト集などでカラー印刷になる場合はそれなりのコストがかかってきます。
また、発注部数が多ければ多いほど1部あたりの印刷費は安くなり、納期も短納期より長い方が印刷費を安く抑えられます。
ZINEの作り方

実際にZINEを制作する場合、どのような流れで制作を進めていけば良いのか、事前に把握しておくことも大切です。ここでは、ZINEの作り方と流れについて解説します。
1.テーマを決める
まずは自分がZINEを通して何を発表したいのか、何を伝えたいのかを明確にし、テーマを決めます。
利益を出すことを目的としていないため、いろいろな人に読まれるか・読まれないかよりも、自分が書きたいか・書きたくないかを重点にテーマを決めてみてください。
テーマが決まったら、制作するZINEのタイプも決めておきます。ZINEは自由な形式で表現できますが、大きくアート系・読み物系・資料系の3つに分類できます。
アート系はイラスト集や写真集、画集、詩集など、アート作品をまとめたものです。
読み物系はテキストが中心で、小説やエッセイ、マンガなどが含まれます。1つのテーマに絞って持論を展開するような作品などもみられます。
資料系も読み物系に近いですが、図鑑などのようにより詳しい知識や情報が掲載されたものを指します。
様々な種類の中から、どのようなイメージで表現したいのかを考えてみてください。
2.構成・台割を決める
次に構成と台割を決めます。構成は、テーマに対してどのような内容をZINEに掲載するのかを決めていきます。
1つのテーマだけで構成するのも、オムニバス形式でいろいろなテーマを扱っても良いかもしれません。
構成が決まったら台割も考えます。台割とは、それぞれのページに対してどの内容を掲載するのか割り振りを決めることです。
デザインなどは後で考えるとして、どのような順番で掲載するのか、写真をどの辺に配置して、文章をどれくらい書くのか、などを決めます。
3.素材を用意する
構成と台割が決まり、制作するZINEの大まかなイメージが固まったら、実際に使用する素材を用意していきます。
文章や写真、イラストなど、原稿に入れる素材を準備していってください。
なお、ZINEに使う素材を用意する際に注意したいのが、著作権です。ZINEを制作する上で特別な制約はありません。
しかし、販売・展示・配布を行う場合は素材の著作者に許可を取る必要があります。
個人だけで楽しむ分には許可を取る必要はないものの、誰かに渡す場合は営利・非営利を問わず著作権侵害が問われてしまうので注意してください。
また、著作権侵害にならないようにフリー素材を使用する人もいますが、フリー素材にも種類があり、非営利目的の場合のみフリーで使用できる素材もあります。
もしその素材が使われたZINEを販売すると、ガイドライン違反になってしまうので、フリー素材であっても必ず規約を確認してください。
4.サイズやレイアウトを決める
次に、ZINEのサイズやレイアウトを決めていきます。一般的にはA5サイズが多いですが、制作者によって自由に決めることが可能です。
ただし、ZINEのイベントに参加する場合、A4サイズ以上だと対象外になる可能性もあるので注意してください。
イベントに参加する予定がない場合は、A4サイズより大きく作っても問題ありません。逆に豆本のような小さいサイズで制作してみるのもおすすめです。
5.印刷、製本する
ZINEの原稿データが完成したら、印刷・製本を行います。自宅にプリンターがある場合はそのまま印刷でき、あとはホチキスで止めるだけで完成です。
自宅にない場合でもコンビニのプリンターを活用すれば、様々なサイズで原稿を印刷できます。
ページ数が多い場合や配布・販売する部数を増やしたい場合、本格的に製本してみたい場合は、印刷業者に依頼するのがおすすめです。
データを入稿し、モノクロ・カラーやサイズなどを決めるだけで、プロの技術で製本してもらえます。
また、紙媒体を選べるところも多く、紙の質感にまでこだわりたい場合にも適しています。
業者に依頼して製本を行う場合には、小ロットからの注文にも対応してくれる業者を選ぶようにしてください。
6.ZINEを配布・販売する
ZINEが完成したら、配布または販売をしてみましょう。
例えば、同じ趣味を持つ友人にだけ配ったり、イベントに参加して販売してみたり、様々な方法でZINEを届けることができます。
ZINEを販売する場合は価格を設定することになりますが、一般的には500~1,000円が相場となっています。
1,000円以上に設定することもできますが、手に取ってもらいづらくなるので注意が必要です。
ただし、希少性の高い情報や独自性の強い作品などは、1,000円以上に設定されていても購入されるケースは多いです。
ZINEの販売方法

自分だけのために制作しても良いZINEですが、より多くの人に届けたいという人もいます。ZINEをより多くの人に届けたい場合は、以下の販売方法を取り入れてみてください。
ZINEのイベントに参加する
多くのZINEが集まるイベントに参加・出展する方法があります。
イベントに参加すると、読者と直接交流することができ、ZINEの内容について直接プレゼンしたり、読者からその場で感想を聞けたりするなどのメリットがあります。
交流を増やせたり、新しいコミュニティを形成したりできるのも魅力です。
また、自分も気になるZINEを購入したり、ほかの制作者とつながりを持ったりすることも可能です。
ネットショップで販売する
ZINEを販売するのにネットショップを活用するのもおすすめです。
自分の作品を販売しているECサイトを1から構築しても良いですが、冊子やオリジナル作品を販売できるプラットフォームを活用することで、より手軽にZINEを販売できるようになります。
例えば「BASE」や「しまうまマルシェ」、「Creema」などが挙げられます。
ZINE専門のショップで販売してもらう
東京や大阪などを中心に、ZINEを取り扱うショップが増えてきています。そのショップのオーナーに依頼し、ショップに置いてもらうことも可能です。
ショップに置いてもらうには、まずZINEを作っていることを伝え、興味を持ってもらえたら実際に見てもらいます。
この時、購入してもらうのではなく配布感覚で見てもらうのが良いでしょう。
そのショップでは扱ってもらえなかったとしても、オーナーからの紹介で取り扱ってもらえそうなショップを紹介してくれる可能性があります。
まとめ・自分の好きなことや表現したいことをZINEで形にしよう
ZINEは自分の考えや気持ちなどを自由に表現できる冊子です。
自分の好きな形で気軽に表現でき、しかもインターネットで表現するのとは違い、形に残すことができます。
また、ZINEを通してこれまでの作品をまとめたポートフォリオを作ったり、自分が手がけた商品のプロモーションやブランディングに活用したりすることも可能です。
自分の好きなこと・表現したいことを、ぜひZINEで形にしてみてください。
創業手帳(冊子版)は、起業やビジネス、経営に役立つ情報を掲載しています。副業に関する情報もまとめているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)