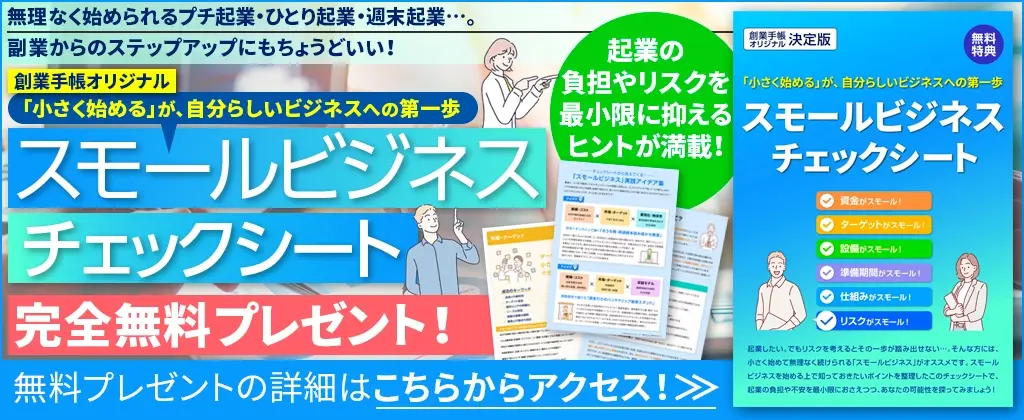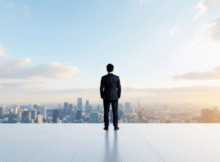自宅ではじめる小さなパン屋さんの開業ガイド|低予算・副業でも可能?
「小さなパン屋さん」を自宅からはじめたい人必見!

「小さなパン屋さん」は、多くの人が魅力を感じる仕事のひとつです。
しかし、店舗やテナントを探すには時間も費用もかかります。低コストでスピーディーに開業するのであれば、自宅ではじめるパン屋さんがおすすめです。
自宅でのパン販売は営業許可と設備投資が必要ではあるものの、柔軟な営業ができます。
副業や退職後のスモールビジネスや趣味を収入源に変えられる魅力的なビジネスモデルとして、自宅でのパン販売が注目されています。
本記事では、自宅ではじめるパン屋の開業方法、必要な準備や費用、副業との両立のポイントまでわかりやすく解説します。
自宅パン屋のようなスモールビジネスは、アイデア次第で大きな可能性があります。ただし、限られたリソースで効率よく運営する工夫も欠かせません。
創業手帳では『スモールビジネス・チェックシート』を無料提供中。小さく始めてしっかり育てるためのヒントをまとめています。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
自宅でパンを販売するために必要なこと
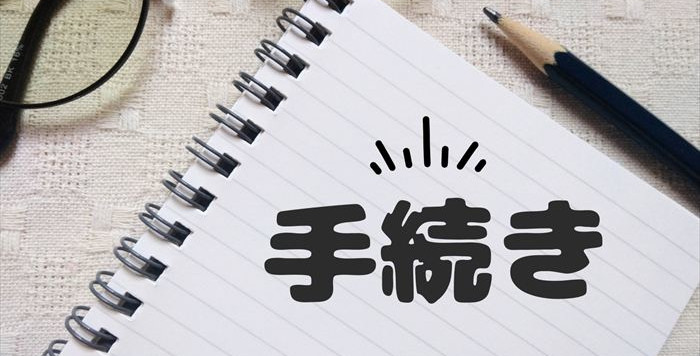
自宅でパンを販売すると聞いても、一切の準備なくいきなりパンを焼いて売っていいわけではありません。自宅でパンを販売するために必要なことをまとめました。
保健所との事前相談が必須
パン屋を開業する時には、必ず営業許可が必要です。パン屋営業では、「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」が関連します。
営業許可申請をする前には、保健所職員と設備や衛生管理について詳細な打ち合わせを行います。
自宅の構造や近隣への影響を考慮した営業計画の提出が求められる場合もあるので、スケジュールに余裕をもって相談してください。
許可を取得してからも定期的な立入検査があるので、継続的な衛生管理体制を構築することが大切です。
調理専用スペースの確保
パン屋を営業するために、調理専用スペースも確保しなければいけません。必要な設備は、厨房設備と衛生設備に分けられます。
家庭用キッチンとは完全に分離した調理専用スペースの設置が営業許可の条件です。
調理場は手洗い設備や二槽シンクの設置が求められ、家庭用設備では要件を満たせません。
調理場の床や壁は清掃しやすい材質にする必要があるので、その改装費用も見込んでおくようにしてください。
食品衛生責任者の資格取得
営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の資格と施設基準を満たすことが求められます。
食品衛生責任者の資格を取得するには、各都道府県の食品衛生協会が実施する講習会を受講しましょう。
調理師や栄養士、製菓衛生士といった資格の保持者は講習免除となる場合があるため事前に確認してください。
食品衛生法上の営業許可
自宅でパンを販売するには菓子製造許可が必須です。保健所への申請前に設備や衛生管理体制を整える必要があり、許可取得までは数週間かかることもあります。
地域によって許可条件が異なるので、管轄の保健所に出向いて詳細な要件を確認しておきいてください。
火災保険・PL保険の加入検討
パン屋開業の時には、保険についても考えておいてください。
まず、自宅での業務用機器を使用するので火災リスクが高まります。火災保険の見直しや事業用保険への加入を検討してください。
さらに食中毒や異物混入による損害賠償リスクに備えて、PL保険(生産物責任保険)も考えなければいけません。
PL保険とは、提供した商品やサービスに欠陥や不備があって購入者に損害が生じた場合に補償をしてくれる保険です。
個人事業主向けの包括的な事業保険が各保険会社から提供されているので、必要な補償内容やオプションを比較してください。
開業届・青色申告承認申請書の提出
個人事業主は、事業開始から1カ月以内に税務署へ個人事業の開業届出書を提出するよう義務付けられています。
また青色申告を選択するには、青色申告承認申請書を提出します。
青色申告にすると最大65万円の青色申告特別控除が受けられて経費計上の幅が広がる一方、複式簿記で帳簿をつけなければいけません。
不安がある場合には、青色申告に対応した会計ソフトの導入も検討しましょう。
事業用の銀行口座開設や帳簿作成など、税務管理の基盤整備も並行して進めるようにしてください。
食材仕入れルートの確保
事業を継続するためには、安定した品質の食材を継続的に調達できる仕入れ先の確保も必要です。
業務用食材卸業者との取引開始には、与信審査や最低発注量の条件設定がある場合も少なくありません。
事業計画の段階で食材を仕入れるためにどういったルートがあるか調べておくようにしてください。
同業他社との差別化につなげるには、地産地消や有機食材など特色ある仕入れルートの開拓も検討する価値があります。
必要な設備と初期費用の目安

自宅でパン屋を開業する場合、物件を借りる費用はかからず、初期費用の多くを設備費用が占めます。自宅パン屋に必要な設備は主にオーブン、発酵器、作業台です。
初期投資は開業時に必ずぶつかる壁ではありますが、工夫次第で抑えることができます。
段階的に設備を充実させていくといった方法も検討してください。以下ではパン屋開業で必要な設備を紹介します。
オーブン(業務用でなくても可)
パンを焼くためには、必ずオーブンは必要です。オーブンは家庭用オーブンでも営業許可は取得可能です。
ただし、連続使用に耐えられて焼きムラなどがない機種を選ぶ必要があります。
業務用オーブンは30万円以上するものの、中古や家庭用上位機種なら5万円程度で導入可能です。
小さなオーブンを使うと一度に焼ける量が限られるため、予約制や少量生産での営業スタイルが現実的かもしれません。
発酵器(または簡易温室)
パンを発酵させるには温度と湿度の管理が重要です。品質を安定させるには、専用の発行機や簡易温室を使います。
市販の発酵器は5〜20万円程度で購入可能です。ただし、保温庫や電気毛布で代用する方法もあります。
高い品質の商品を提供し続けるために、季節による温度変化を考慮して、安定した発酵環境を確保してください。
作業台・ミキサー・冷蔵庫など
衛生的な環境を保つためには、清潔を保てる材質の作業台も必要です。ステンレス製作業台は、1万円台で購入できるものもあるのでサイズを確認して購入してください。
さらに、生地作りには業務用ミキサーや業務用冷蔵庫があると便利ですが、家庭用を使うことで費用を抑えられます。
設備をそろえるのが困難な時には、必要最低限の設備でスタートして段階的に導入していく方法もあります。
自宅でのパン販売に向いている人・スタイル

自宅でのパン販売は、設備投資を最小限にしてパン屋開業の夢をかなえられる方法です。しかし、誰にでも向いているとはいえません。
自宅でのパン販売に向いている人、営業スタイルについて紹介します。
パン作りが趣味で一定の品質を提供できる人
前提として、パンを販売するためには、パン作りの技術が必要です。
基本的な製パン技術を習得しており、安定した品質のパンを安定して作れる技術力は身につけておかなければいけません。
趣味としてパン作りをしてきたとしても、開業のためにはお客様に提供するレベルの品質管理ができ、衛生面でも責任を持てる意識が求められます。
趣味レベルから商品レベルへの品質向上を目指すのであれば、パン屋で働いたり、専門学校に通ったりして修行することも検討してください。
家事や子育てと両立したい主婦・シニア層
自宅でのパン屋を開業するスタイルは、ライフスタイルに合わせて働きたい人のニーズに適しています。
自宅での営業なら通勤時間がなく、家事や育児の合間に作業時間を確保可能です。
また、子どもの学校行事や介護などの都合に合わせて営業日を調整できる柔軟性があるのでライフスタイルの変化にも対応できます。
人生経験を活かした接客や、地域密着型の温かい営業スタイルといった自分らしい働き方を目指す人にもおすすめです。
副業で週1〜2回だけ営業したい人
自宅のパン屋は、パン屋のための物件取得費や光熱費といった費用が発生しません。そのため、本業を持ちながら週末だけの営業で収益を上げたい場合にも適しています。
営業頻度を抑えられるので、品質管理や商品開発に集中できて差別化でき、ほかにはない商品を生み出せる点もメリットです。
将来的に店舗を開くとしても将来の準備段階として、リスクを抑えながら経験を積めるでしょう。
販売方法は?インターネット×リアルで広がる販路

自宅でパン屋を開業する場合、そもそもどうやって販売するのかが問題となります。どのようにして販売すればいいのか、インターネットとリアルの販路について紹介します。
SNS+予約販売
できるだけ費用をかけずに認知度を高めるのであればSNSを活用した販売をしましょう。
具体的には、Instagramで商品写真を投稿してDMやコメントで予約を受け付ける仕組みがおすすめです。
SNSはすぐに情報を拡散できるので、定期的な投稿でファンを増やし、限定商品や季節メニューで購買意欲を高められる点も魅力です。
予約制であれば食材ロスを削減でき、無駄なコストを削減できます。
インターネットで認知度を高められて、お客様との直接的なコミュニケーションも図れる手法です。
近所での直接販売・委託販売
近隣住民への直接販売は口コミ効果が高く、安定した顧客基盤を築きやすい手法です。
店舗を買ったり借りたりすると開業費用は大きくなってしまいますが、地域のカフェや雑貨店への委託販売なら、店舗を持たずに販路を拡大できます。
委託先との良好な関係を築ければ、長期的な取引パートナーシップを形成でき安定した事業が可能な方法です。
マルシェ・イベント出店
週末のマルシェやイベント出店は新規顧客獲得の絶好の機会です。多くの人に対面で商品の魅力を直接伝えられるので、ブランド認知度の向上につながります。
マルシェやイベントに出店する利益は売上だけではありません。ほかの出店者との交流により、販路拡大のヒントや協力関係を獲得できます。
インターネットショップ(BASE・STORESなど)
自社の商品を広い知識の人に届けるのであれば、インターネットショップもあります。冷凍パンや焼き菓子なら全国への配送が可能で、販売エリアを大幅に拡大可能です。
ショッピングカート機能がある自社ホームページも、インターネットショップ作成サービスを利用すれば専門知識がなくても手軽に開設可能です。
ただし、食品の販売には一定の食品表示法に基づく原材料表示やアレルゲン情報の記載が法的に義務付けられています。
ラベルの表示項目も定められているので管轄の保健所でも相談しておくようにしてください。
副業で自宅パン屋を続けるコツ

副業として自宅パン屋を続けることは、決して簡単ではありません。継続している人にはどのような違いがあるのか、コツを紹介します。
無理のない営業スタイル
副業として自宅パン屋をはじめる時には、無理をしない規模にするようにします。まずは、週1〜2回の営業頻度に設定し、本業や家庭生活との両立を最優先に考えてください。
食材ロスや過労を防ぐには、完全予約制にして生産量を調整する方法も効果的です。さらに、営業日を固定化して顧客の購買習慣を作り上げると売上げが安定します。
口コミとリピート重視
副業であっても、パン屋として丁寧な接客と安定した品質の商品提供は必須です。顧客満足度を最大化するために口コミやリピート率には気を配ってください。
季節のおまけや手書きメッセージなど、心のこもったサービスで顧客満足度を高める方法も効果的です。
満足した顧客からの口コミは最も効果的な宣伝となり、新規顧客獲得につながります。
価格設定は利益確保を意識
利益を出すために材料費、人件費、光熱費、配送費を含めた原価計算を正確に行う必要があります。
適正な利益率を確保しないと事業継続が困難になるため、安易な価格競争は避けてください。
必ずしも安ければいいわけではなく、品質に見合った価格設定が重要です。ブランド価値を高め、持続可能な経営を目指してください。
注意点とトラブル回避のポイント

パン屋の開業は、ポイントを押さえておけば軌道に乗せられる仕事です。トラブルを回避するためにできることをまとめました。
無許可営業はトラブルや罰則の原因に
パン屋の営業は、必ず食品営業許可を取得して行います。営業許可なしでパンを販売すると食品衛生法違反となり、罰金や営業停止処分を受けます。
許可取得には時間と費用がかかりますが、合法的な営業のために必ず事前に取得してください。
さらに近隣住民からの通報により保健所の立入検査を受けると、事業継続が困難になる可能性もあります。開業して営業がスタートしてからも細心の注意を払ってください。
衛生管理・食品表示義務にも注意
食品を扱う以上、衛生管理は必須です。調理場の清掃や食材の温度管理など、日常的な衛生管理体制の構築を構築しなければいけません。
食中毒事故が発生すると営業停止や損害賠償責任を負い、事業継続ができないこともあります。
原材料名、アレルゲン情報、消費期限といった食品表示義務は法的義務なので、間違いがないように徹底してください。
個人情報・配送ミス・SNS炎上にも備える
顧客の個人情報は適切に管理しなければいけません。第三者への漏洩しないように事前に対策を講じたほうが良いでしょう。
具体的には、配送先の間違いや商品の破損などのトラブルに備えて、対応マニュアルを準備しておいてください。
SNSでの不適切な発言や対応が炎上につながる可能性があるため、情報発信は慎重に行います。
補助金・支援制度も活用しよう

自宅でパン屋を営業するには、補助金や支援制度の活用も考えてください。自宅でパン屋を開業する時にどういった制度を活用できるのかまとめました。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、必要な販路開拓や生産性向上にかかる費用の一部を補助金として受給できる制度で初期費用の負担を大幅に軽減できます。
申請するには、経営計画書と補助事業計画書を作成して地域の商工会、商工会議所窓口に提出して、事業支援計画書を受け取る必要があります。
まずは所轄の商工会、商工会議所に相談してください。
女性、若者/シニア起業家支援資金
女性、若者/シニア起業家支援資金は、女性、35歳未満の若者、または55歳以上のシニアの人で新規開業からおおむね7年以内の人を対象にした融資制度です。
低金利での利用が可能で、特定の条件を満たせば担保や保証人が不要となる特例が適用されるため、自己資金が少ない場合でも開業資金を調達しやすくなります。
オーブン、ミキサーなどの設備資金や材料費、光熱費といった運転資金として最大7,200万円まで借入れが可能です。
長期(設備資金20年以内、運転資金7年以内)での返済計画が立てられます。
まとめ|パン作りの楽しさを”自分の店”に変える
自宅で開業するパン屋は、趣味と収入を両立できる理想的なスモールビジネスとして注目されています。
適切な準備と法的手続きを経れば、リスクを抑えながら夢の実現に近づく事が可能です。
自宅で小さくはじめて段階的に成長させることで、持続可能な事業として育てていけるでしょう。
まずはどのようなパン屋を始めたいかイメージを固めてから必要な手続きをピックアップしてみてください。
自宅パン屋をスタートするのは「小さく始めて大きく育てる」第一歩。
創業手帳の『スモールビジネス・チェックシート』には、リスクを抑えつつ将来の成長を見据えたヒントが載っています。開業の前に目を通しておくと安心です。
(編集:創業手帳編集部)