シェアハウス経営とは?メリット・デメリットから費用相場まで徹底解説!
シェアハウスのニーズは増加傾向にある

近年、若者や単身赴任者、さらには外国人留学生などを中心に「シェアハウス」の需要が高まっています。
東京シェアハウス合同会社のデータによると、シェアハウスの問い合わせ数の推移はコロナ禍で一時的に落ち込んだものの、2024年8月末時点で33,369件の反響があり、過去最高水準に達していることがわかっています。
こうした背景から、アパートやマンションの空室対策として「シェアハウス経営」に注目するオーナーも増えてきました。
しかし、シェアハウス経営には安定した収益が見込めるメリットがある一方で、運営コストや入居者トラブルといったリスクも存在します。
この記事では、シェアハウス経営のメリット・デメリット、さらに初期費用や運営費用の相場について詳しく解説していきます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
シェアハウス経営とは?

シェアハウス経営とは、1軒の建物に個室と共用設備を用意して、複数人に部屋を貸す不動産経営を指します。
リビングやキッチン、バスルームなどは共用設備となっており、入居者同士で交流を図ることが可能です。
また、個人の部屋もきちんと用意されており、交流を図りながらもプライバシーを保てるようになっています。
一般的なアパート・マンション経営は普通建物賃貸借契約を結ぶのが一般的ですが、シェアハウス経営の場合は借地借家法に基づき定期建物賃貸借契約を結ぶことが多いです。
定期建物賃貸借契約になると、契約期間の満了に伴い契約は終了となります。
ルームシェアやゲストハウスとの違い
シェアハウスと似ているものとして、ルームシェアやゲストハウスがあります。ルームシェアとは、1つの賃貸物件に対して複数人が住んでいる状態です。
シェアハウスでは入居者全員が個別に契約を結んでおり、一人ひとりから家賃を受け取ることになりますが、ルームシェアだと代表者のみ契約を結び、家賃を支払うことになります。
ゲストハウスとは、簡易的な宿泊施設を指します。ホテルとは違いトイレやバスルームなどが共用なので、一見シェアハウスと似ているように感じられるかもしれません。
しかし、ゲストハウスはあくまで宿泊施設であり、シェアハウスのように長く住むことを想定していません。数カ月程度の中長期滞在に活用されることが多いです。
なお、法的に明確な違いは定義されていないため、中には年単位での長期利用で使われているゲストハウスも存在します。
シェアハウス経営の収益性
シェアハウス経営を始める上で気になる収益性ですが、1つの住居に複数人が暮らし、その入居者全員から家賃を支払ってもらうことになるため、収益性は比較的高いといえます。
例えば1部屋が空室だったとしても、他の部屋に入居者がいればその分家賃収入を得られるので、安定した経営につながります。
また、シェアハウスは一般的なアパート・マンションに比べて、狭い部屋でも需要があります。
例えば、アパートだと1部屋22~25㎡の面積を確保する必要がありますが、シェアハウスなら10㎡未満でも問題ありません。
なぜなら、キッチンやバスルームなどは共用設備として備えることになるので、その分の面積が不要となるためです。
狭い部屋なら1部屋あたりの㎡単価も高くなりやすく、収益性も高まりやすいといえます。
シェアハウス市場の動向

シェアハウス経営を考える際に、市場の動向も把握することが重要となってきます。2020年からのコロナ禍によって、一時的にシェアハウスの市場規模は縮小してしまいました。
しかし、コロナ禍が明けてからの反響は大きく、2024年も市場規模の拡大傾向にあります。
シェアハウスの市場規模が拡大傾向にある背景に、外国人からの需要が高い点が挙げられます。
訪日外国人旅行者数はコロナ禍が本格的に明けた2023年時点で2,507万人、2024年には3,687万人と、すでにコロナ前(2019年)の3,188万人を超えているのです。
日本での中長期滞在を計画している外国人にとっては、数カ月~1年程度ホテルに滞在するとなると、かなりの金額が必要となってきます。
一方、シェアハウスであればホテルよりもコストを抑えられ、なおかつ日本の住まいや暮らしまで体験することが可能です。
また、シェアハウスには同じく日本を訪れた訪日外国人や、外国語を学んでいる日本人などが入居している場合もあるため、交流を深められる点も魅力に感じる人が多いと考えられます。
シェアハウス経営の始め方・運営の流れ

シェアハウス経営を行いたい場合、どのように始めれば良いのでしょうか。ここで、始め方と運営の流れを解説します。
物件選びと購入・賃貸の検討
シェアハウス経営を始める上で、まずはシェアハウスに適した物件を選ぶ必要があります。シェアハウスに適した物件の条件として、以下の項目が挙げられます。
-
- ある程度広い面積がある
- 個室が複数ある
- リビングやキッチンなどが広い
例えば複数人が生活を共にしても十分なスペースがある広めの一戸建ては、シェアハウス経営に向いています。
リノベーションや設備投資
空き家などを活用してシェアハウス経営を行う場合、リノベーションや設備投資が必要になります。
また、中古のアパートをリノベーションによってシェアハウスに転用することも可能です。
1部屋を個室ではなく共用スペースとすることで、交流できるスペースと個人のスペースを明確に分けられます。
シェアハウス転用に向けてリノベーションを行う場合には、入居者同士のトラブルを防ぐために防音対策は必須です。
共用リビングに人が集まりやすいことから、寝たいのに話し声がうるさくて眠れなかったり、個室で電話をしていたら壁が薄くて隣の部屋の人に聞かれていたりする場合もあります。
また、水回り設備も入居者数を考え、複数準備しておくことも念頭に置かなくてはなりません。
例えばトイレやシャワールーム、洗面台などはすべて共用となるため、特定の時間に混みあってしまうと不満が上がる可能性があります。
入居者募集の方法
シェアハウスに入居者を募集する場合、以下の方法で募集をかけることが多いです。
-
- シェアハウス専用のポータルサイトに登録する
- 管理会社に委託する
- SNSから募集をかける
- 口コミや紹介をしてもらう
賃貸物件を検索できるポータルサイトには、シェアハウス専用のポータルサイトもあります。
中には外国語で登録できるサイトもあるため、外国人需要にも対応することが可能です。
また、シェアハウスの管理を管理会社に委託する場合は、入居者募集もすべて管理会社が行ってくれます。
ポータルサイトへの登録はもちろん、管理会社のホームページにも情報を掲載し、入居者を集めてくれるので安心です。
オーナー自ら入居者の募集を手がけたい場合は、SNSを活用するのがおすすめです。SNSから物件の最新情報や空室情報などを掲載し、入居者を募集している旨を呼びかけます。
シェアハウスに入居を希望する人は比較的年齢が若い傾向にあるため、若い年齢層のユーザーが多いSNSで募集することで、入居希望者も集まりやすいでしょう。
管理・運営の流れ
オーナーだけでシェアハウスを管理するのは難しい場合、管理会社に委託することになります。
委託するのに費用はかかってしまうものの、シェアハウス運営において様々な対応をしてもらえます。
-
- 入居者募集
- 家賃や共益費の集金、入金確認
- 契約の更新、再契約の手続き
- 建物の維持管理
- 緊急時の対応
- 入居者からの問い合わせ対応・コミュニティ管理
- 近隣対応
- 退去手続き など
シェアハウス経営にかかる費用相場

シェアハウス経営を始める場合、どれくらいの費用がかかってくるのかも気になるところです。ここでは、シェアハウス経営の初期費用と維持費用の相場を解説します。
初期費用の相場
シェアハウス経営にかかる初期費用は、物件にどれくらいの金額をかけるかによって大きく異なりますが、それ以外の費用だと以下が目安となります。
リフォームの工事費:200~300万円程度
家具・家電の購入費:100万円程度
諸費用:中古物件の場合購入価格の7%程度、新築物件の場合購入価格の5%程度
例えば中古の一戸建てを2,000万円で購入した場合、初期費用の目安は以下のとおりです。
物件購入費:2,000万円
リフォームの工事費:200万円
家具・家電の購入費:100万円
諸費用:2,000万円×0.07=140万円
初期費用合計:2,440万円
なお、諸費用には不動産取得税や登録免許税などの税金以外にも、火災保険料や融資手数料、司法書士に支払う報酬などが含まれています。
維持費用の相場
シェアハウスを運営してからかかる費用の相場は、毎月の家賃収入の20~30%程度です。維持費用の内訳は以下のとおりです。
- 【毎月かかる費用】
-
- 管理委託費
- 共益費(入居者から徴収)
- ローン返済金
- 【年間でかかる費用】
-
- 固定資産税
- 都市計画税
- 【都度かかる費用】
-
- 原状回復費
- 保険料
- その他雑費
例えば毎月の家賃収入が合計50万円だった場合、10万円~15万円は維持費用として出ていくお金になります。
ただし、原状回復費などは都度発生する費用になるため、家賃収入の20~30%では収まらない可能性もあります。
シェアハウス経営を手がけるメリット

シェアハウス経営は、一般的な賃貸経営と異なりどのようなメリットがあるのでしょうか。シェアハウス経営を手がけるメリットには、主に以下の5つが挙げられます。
空室リスクを抑えやすい
シェアハウスは、アパート・マンション経営と比べて空室リスクを抑えやすいというメリットがあります。
1つの物件に複数の入居者が共同で生活するシェアハウスは、1つ部屋が空いたとしても、他の入居者がいるため家賃収入は確保できます。
シェアハウスではなく戸建て賃貸として貸し出した場合、退去されるとそこで家賃収入が途絶えてしまい、入居者が入るまでゼロの状態になってしまうのです。
収益性が高い
シェアハウスは収益性が高いのも大きなメリットです。
上記で紹介したように、1部屋あたりの㎡単価が高くなりますが、さらにシェアハウスの需要は拡大傾向にあるため、退去されてもすぐに入居者が入ってくることが期待できます。
また、シェアハウスの家賃は共用スペースや家具・家電の提供などで魅力的な住空間を構築すれば、多少高く設定したとしても問題なく入居者が集まるケースもあります。
ターゲット層の幅が広がる
シェアハウスは20代~30代を中心に、学生や社会人、外国人留学生や観光客、単身赴任のビジネスマンなどが集まりやすいです。
特に外国人観光客からの需要は、一般的なアパートやマンションだと獲得が難しいですが、シェアハウスであればインバウンド効果を実感することもあるでしょう。
一般的な賃貸物件と差別化しやすい
アパートやマンションに比べて、シェアハウスは独自のコンセプトを持っているケースが多くみられます。
異文化交流を目的に外国人が多いシェアハウスや、起業家が集まるシェアハウス、トレーニングルームを完備した健康志向の人向けのシェアハウスなどです。
こうしたコンセプトを明確に定めることで周囲の賃貸物件と差別化ができ、入居者も集まりやすくなります。
建物にデメリットがあっても経営しやすい
個室が狭い、築年数が周りの物件と比べて少し古いなど、建物にデメリットがあったとしても、シェアハウスにすれば経営はしやすくなります。
特に個室が狭かったとしても、共用スペースを広く取ることで納得して入居してもらえる可能性が高いです。
そもそもシェアハウスは他の入居者との交流を求めて利用する人が多いため、建物のデメリットは目立ちにくくなります。
シェアハウス経営を手がけるデメリット

シェアハウス経営には様々なメリットがみられる一方で、デメリットに感じてしまう部分もあります。
管理業務の手間がかかる
シェアハウスはアパートやマンションに比べて管理業務の手間がかかりやすいです。
例えば共用スペースの清掃や設備点検、消耗品の補充など、定期的に行っていないとすぐに汚くなったり、在庫が切れてしまったりする場合も少なくありません。
また、シェアハウスを運営する際には入居者がお互いに気持ち良く暮らせるよう、生活のルールも設定する必要があります。
家具・家電を備え付けで用意する必要がある
アパートやマンションであれば、一般的に家具・家電などを備え付ける必要はありません。
しかし、シェアハウスの場合は共用スペースだけでなく、個室スペースにもベッドやイスなどを備え付けておくのが一般的です。
これらの家具・家電は初期費用としてかかってくるだけでなく、経年劣化で故障した場合の修理・交換費用もすべてオーナーが負担することになります。
都市部以外での運営は難しい
シェアハウスを希望する人は若者や外国人が多いということもあり、都市部以外の地域だと入居者が集まりにくく、運営が難しいというデメリットもあります。
特に地方だと一般的なアパートやマンションでも家賃は安く抑えられており、1人で快適に過ごせるアパートやマンションのほうが需要も高くなる傾向にあります。
入居者同士のトラブルが発生しやすい
シェアハウスは、いくら個室があったとしても毎日他の入居者と顔を合わせることになるため、入居者同士でトラブルが起きてしまうことも珍しくありません。
トラブルが発生した場合、基本的には管理会社が対応することになりますが、オーナー側も未然に防ぐために、入居者と話し合いをする機会を定期的に設けることも大切です。
入居者同士のトラブルを完全に避けることは困難ですが、対策を講じてくことで安定した経営につながります。
まとめ・シェアハウス経営で安定した収益の確保を目指そう
コロナ禍が明けてから需要はさらに拡大し、不動産投資の中でも注目されているシェアハウス経営。
収益性の高さや空室リスクを抑えやすいこと、明確なコンセプトを設けることで周りの賃貸物件と差別化がしやすいなどのメリットがあります。
ただし、初期費用がかかりやすい点や入居者同士のトラブルが発生しやすい点など、デメリットもあります。
シェアハウス経営で安定した収益を確保するためにも、事前の準備と信頼できる管理会社を見つけることが重要です。
シェアハウス経営を本気で検討するなら、まずは『創業手帳(無料)』で全体像を整理しませんか。
ビジネスを始めるうえで抑えておくべきポイントを1冊に集約。無料でお届け致します。
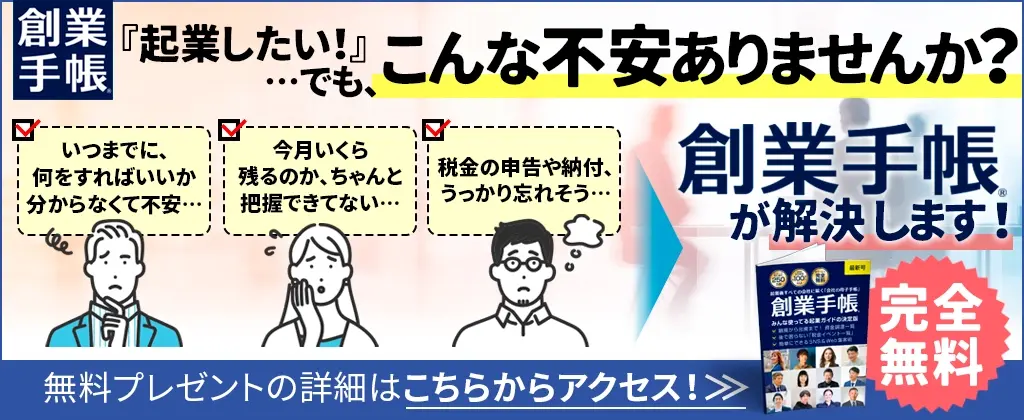
(編集:創業手帳編集部)




































