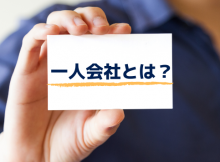メンバーシップ型雇用とは?ジョブ型雇用との違いをわかりやすく解説
雇用システムの種類を理解しよう

日本国内の雇用システムは高度成長期に誕生したとされており、終身雇用を前提とした「メンバーシップ型雇用」が主流です。
メンバーシップ型雇用を取り入れている企業は多くみられますが、近年はメンバーシップ型雇用とは異なる「ジョブ型雇用」も採用されています。
今回は、メンバーシップ型雇用の特徴や普及した背景を解説しつつ、ジョブ型雇用との違いを紹介します。
雇用システムについて知りたい人や、自社の雇用システムについて検討している人はぜひ参考にしてみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
メンバーシップ型雇用とは?時代遅れ?

メンバーシップ型雇用は、これまで国内の企業で多く採用されてきた雇用システムです。具体的にどのような特徴があるのか解説していきます。
メンバーシップ型雇用は日本独自の雇用システム
メンバーシップ型雇用とは、戦後に誕生した日本独自の雇用システムです。企業が人材を採用する際に、職務・勤務地などを限定せず雇用契約を結びます。
始めに総合職の仕事を学んでから、転勤・異動などを繰り返し、長期的に人材を育成していくことが特徴です。
新卒を数十人~数百人単位でまとめて採用を行っている企業は、メンバーシップ型雇用を採用しているといえます。
メンバーシップ型雇用は長期雇用を前提としているため、定年を迎えるまで従業員を雇用する「終身雇用制度」や、年齢・勤続年数に合わせて昇給・昇格を行う「年功序列制度」と良い相性です。
また、メンバーシップ型雇用の場合、従業員に対して仕事を合わせる働き方ともいわれています。
メンバーシップ型雇用が普及した背景
メンバーシップ型雇用が普及した背景には、戦後に訪れた高度経済成長期による影響があります。
1950年代半ばから約20年にわたって、日本経済は高い伸び率で上昇していきました。
重化学工業が発展するにつれ工場も次々に建設され、地方から大都市に向けて若者が続々と就職のために集まる「集団就職」が活発に行われていきました。
また、高度経済成長にともなって、電化製品の普及や高速道路などの建設ラッシュ、インフラ整備などに大量の労働力が必要となり、企業は多くの人材を採用しています。
こうした背景から、新卒者を大量に採用し、長期的に教育して生産性を高めるためにメンバーシップ型雇用は広まりました。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い

ジョブ型雇用とは、企業が求めている職務に応じて、その職務を実行できるスキル・経験・資格などを持った人材を採用する雇用システムです。
従業員に対して仕事を合わせるメンバーシップ型雇用とは異なり、ジョブ型雇用は仕事や必要な職務に合わせて人材を採用していきます。
日本ではメンバーシップ型雇用が普及しましたが、海外ではジョブ型雇用を採用する企業がほとんどです。
これは、海外の企業では新卒者の大量採用が難しいことが関係しています。海外は同じ時期にまとまった人数を採用するのではなく、中途採用がメインです。
こうした理由から、海外ではジョブ型雇用が一般的となっています。
メンバーシップ型雇用のメリット

長年日本の経済を支えてきた企業で採用されてきたメンバーシップ型雇用には、様々なメリットがあります。どのようなメリットがあるのか解説していきます。
長期・計画的に人材を育成できる
メンバーシップ型雇用は、新卒者を採用して長期的に育成し、最終的には幹部候補を育て上げていきます。
終身雇用を前提としていることから、部署の異動で様々な経験を積ませたり、業務に取組みつつ研修を受けさせたりすることも可能です。
多くの業務に携わらせることで、業務や市場に精通するゼネラリストを育成できます。
ゼネラリストは視野を広く持ち、業務を円滑に進める管理職にも向いているため、将来企業を担ってくれる人材を育てられます。
柔軟に人員配置ができる
メンバーシップ型雇用では、従業員一人ひとりの業務内容や範囲が決まっていないため、様々な経験を積んでもらえます。
欠員が出て急遽人手を用意しなくてはいけない場合でも、すぐに従業員を異動して対応することが可能です。
一方のジョブ型雇用では、従業員一人ひとりに割り当てられた業務内容が限定されているため、突然欠員が出た時や方針変更によって強化したい業務があった場合、新たに人材を採用することになります。
採用コストを抑えられる
ジョブ型雇用は、新卒・中途を問わず年間を通して必要な人材を雇用する「通年採用」とですが、求人広告を出したり説明会を開催したりする必要があります。
そのため、要件に見合う人が見つからなければ、広告を長期間出さなければならない場合があるかもしれません。そのため、採用にかかるコストは比較的大きなものになります。
一方、メンバーシップ型雇用の場合は、新卒者をまとめて採用することから、通年採用に比べて採用コストを抑えられます。
チームワークを強化できる
メンバーシップ型雇用は、長期的に人材を育成していくことから、帰属意識を持ちやすいといえます。
「自分はこの会社の一員だ」という意識が高まれば、組織として一体感が出たり会社に対して愛着を持てたりします。
また、責任感が芽生えるため、仕事に対するモチベーションの向上にも期待できるかもしれません。
さらに、従業員同士のつながりも長期間にわたって構築されることから、チームワークを強化できることもメリットです。
チームワークが強化されれば業務の効率化や生産性の向上にもつながります。
メンバーシップ型雇用のデメリット

メンバーシップ型雇用は長期的に人材を育成できる反面、デメリットに感じてしまう部分もあります。ここでは、メンバーシップ型雇用におけるデメリットを解説していきます。
専門職を担える人材不足の懸念がある
メンバーシップ型雇用は、主にゼネラリストを育成するために最適な雇用システムですが、その一方でスペシャリストを育成しにくいという点が挙げられます。
スペシャリストとは、特定の分野における専門職を担える人材のことです。
様々な業務を経験するために各部署への異動が多いメンバーシップ型雇用は、専門性を磨く(みがく)ために同じ部署で長期間働けません。
また、専門性を磨くためには、ある程度長い時間をかけて経験を積む必要もあります。
そのため、専門職を担える人材が辞めてしまった場合、新たに求人を出して専門的な人材を確保する必要があります。
グローバル採用を逃す可能性がある
冒頭でも紹介したように、メンバーシップ型雇用は日本独自の雇用システムであり、海外ではジョブ型雇用が一般的です。
そのため、日本で働きたいと考える外国人であれば、メンバーシップ型雇用が受け入れられず、ジョブ型雇用の企業に入社するケースが多くあります。
このように、メンバーシップ型雇用によってグローバル採用を逃す可能性もあることを知っておくことも大切です。
なお、海外と日本ではの卒業シーズンの時期が異なるため、新卒をまとめて採用するメンバーシップ型雇用では海外の優秀な人材を採用することが難しくなってしまいます。
人件費が上がりやすい
メンバーシップ型雇用は人件費が上がりやすい点も、企業にとってデメリットになります。
メンバーシップ型雇用の場合、終身雇用・年功序列が基本となっていることから、社員の年齢や勤続年数に応じて収入が増えていき、役職も上がっていきます。
そうなると、企業の利益が上がっていなくても、スキルが低い従業員の収入を増やしていくことになります。
また、終身雇用であれば、経営が悪化した際、従業員を簡単に解雇できません。人件費の負担が重くのしかかってしまうことを念頭に置く必要があります。
ジョブ型雇用のメリット

海外で取り入れられているジョブ型雇用は、近年日本企業でも採用されるケースが増えています。ジョブ型雇用にすることで得られるメリットを解説します。
即戦力となる人員を効率良く確保できる
ジョブ型雇用のメリットとして、即戦力になる人員を効率良く確保できる点が挙げられます。
スキルや経験の有無を条件として採用活動を行うことが多く、専門性が高い人材の中から自社に合った人材を採用することになります。
すでに持っている知識や経験などを活かせることから、入社後すぐに即戦力として活躍してくれる可能性が高いです。
また、競合他社よりも早く専門性の高い人材を確保・育成することで、生産性の向上や競合優位性の獲得なども期待できます。
入社後のミスマッチを防げる
ジョブ型雇用の場合、仕事に対して人員を合わせることから、採用活動の段階でその人にやってもらう仕事内容や配属先などが決められています。
求人情報にもその内容が書かれていることから、入社後のミスマッチも防ぎやすいです。
なお、メンバーシップ型雇用であれば、成果が出なくても年齢や勤続年数に応じて給与が上がり続けていきますが、若手社員のモチベーションは下がりがちです。
一方のジョブ型雇用は実力主義のため、従業員同士で切磋琢磨し合う環境も作れることから、仕事へのモチベーションも高い状態で維持できます。
評価がしやすくなる
メンバーシップ型雇用だと、仕事へのやる気や人柄など曖昧な基準で評価し、採用するかどうかを見極める必要があります。
しかし、ジョブ型採用の場合は、実績やスキル、経験などを定量的に評価することも可能で、採用の合否をつけやすいです。
入社後は成果によって従業員を評価することになり、年齢や勤続年数は問わないため、実績を上げた人ほど評価されやすくなり、企業の持続的な成長にもつながります。
ジョブ型雇用のデメリット

即戦力となる人員の確保や入社後のミスマッチ予防、評価がしやすくなるなど、ジョブ型雇用には様々なメリットがあります。
一方で、デメリットになる部分もあるので注意が必要です。ここでは、ジョブ型雇用のデメリットを紹介します。
会社都合での人員の配置が難しい
ジョブ型雇用のデメリットとして、会社都合での人員配置が難しい点が挙げられます。
ジョブ型雇用の場合、求人を募集する段階で職務内容や勤務地などの詳細な条件を盛り込むことから、入社後に別の部署・勤務地へ人員を配置できなくなってしまう可能性があります。
例えば事業の性質的に繁忙期があり人材を強化したい場合でも、別部署から補填するのではなく、その時期に必要な人材を別途確保する必要が出てきます。
また、将来的に特定の業務が不要となった際には、人員を解雇せざるを得なくなる場合もあることに注意が必要です。
転職される可能性がある
ジョブ型雇用はメンバーシップ型雇用とは異なり、与えられた専門性の高い職務を遂行することが基本であり、チームで助け合うという意識や会社に対する帰属意識が形成しにくいとされています。
一方のメンバーシップ型雇用は、長く働けばその分給料が上がるなど、働いている人にとってメリットがあります。
しかし。ジョブ型雇用は長く働いたとしても条件は変わらないことから、より良い待遇の会社へ転職する人も少なくありません。
ジョブ型雇用を取り入れる際には、従業員に長く働いてもらうための工夫が必要となってきます。
採用活動が難しくなる
ジョブ型雇用の場合、職種やスキルなどを重視して採用活動を行うことから、求めている基準によっては採用活動が難しくなる場合もあります。
また、スキルを持つ人材はほかの企業からも必要とされる傾向にあり、人材に対する競争率は高いです。そのため、メンバーシップ型雇用と比べて採用活動は難しいといえます。
さらに、特定の資格を持った人材が退職した場合、代替の人材を確保できるまで時間がかかってしまう場合もあります。
どっちにすべき?メンバーシップ型雇用orジョブ型雇用

ここまでメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用のメリット・デメリットを紹介してきましたが、結局どちらを選べばいいのか迷っている人も多いかもしれません。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用のどちらにするか迷っている場合は、以下の表を参考にしつつ、自社に適した雇用システムを取り入れてください。
| メンバーシップ型雇用 | ジョブ型雇用 | |
|---|---|---|
| 特徴 | 従業員に合わせて職務を充てる | 職務に合わせて雇用する |
| 職務の幅 | 総合的 | 専門的 |
| 業務内容 | 明確化はされていない | 職務記述書で明確になっている |
| 異動・転勤 | あり | 原則なし |
| 労働契約 | 終身雇用 | 終身雇用ではない |
| 採用基準 | 企業が求める人物像に適しているか 長期間会社で働けるか |
企業が求める業務に対して遂行できる力を持っているか |
| 評価基準 | 年齢・勤続年数、業務の成果 | スキル、業務の成果 |
| 報酬 | 年齢・勤続年数などに応じて報酬が変わる | 業務の成果に応じて契約更新時に変わる |
| 採用 | 新卒一括採用が基本 | 中途採用が基本 |
| 育成 | 会社が用意した研修などで育成 | 自己研鑽が基本 |
なお、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用を併用することも可能です。
併用することで、長所をうまく融合した独自の雇用システムが生み出せます。
また、新たな制度を導入すると従業員からも反発が起きやすいですが、急速な変化を抑えられ、従業員にも納得してもらいやすくなります。
まとめ・自社に合う雇用形態を取り入れることが大切
これまで国内の企業はメンバーシップ型雇用を採用するケースがほとんどでしたが、近年はジョブ型雇用を採用する企業も増えてきています。
どちらが良いかは各企業の特性や求める人材によっても異なるため、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の特徴を把握した上で、自社に見合った雇用形態を取り入れることが大切です。
また、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の長所を融合し、独自の雇用スタイルを構築することもできます。
メンバーシップ型雇用にも多くのメリットがあることから、うまくジョブ型雇用と融合させる形を取ることも検討してみてください。
創業手帳(冊子版)では、創業者や起業家、個人事業主などに向けて経営に役立つ情報をお届けしています。今回の記事のように人事・経理に関わる内容も紹介しているため、気になる人はぜひチェックしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)