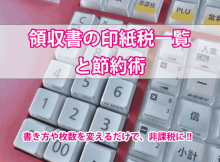金融所得課税引き上げはいつから?制度変更の背景や中小企業への影響を解説
金融所得課税引き上げは中小企業の経営者にも影響する可能性がある!

近年、政府による税制改正の動きが注目を集める中、特に関心を呼んでいるのが「金融所得課税の引き上げ」です。
株式や投資信託などの利益にかかる税率が変われば、個人投資家だけでなく、資産運用を行う中小企業の経営者にも影響がおよぶ可能性があります。
事業資金の運用や将来の資産形成を考える上で、制度変更の内容を正しく理解しておくことは不可欠です。
今回は、金融所得課税引き上げの開始時期や具体的な変更点、そして中小企業に与える影響について解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
そもそも金融所得課税とは?

金融所得課税とは、預金や株式、投資信託などの金融商品からの所得に課せられる税金です。
例えば、保有する株式で配当金を得た場合や、売却益を得た場合などは、金融所得課税の対象に含まれます。
金融所得課税には主に3つの課税方式があります。
-
- 申告分離課税
- 総合課税
- 申告不要
税率は一律20.315%です。利子による所得は自動徴収されるため申告は不要ですが、株式・投資信託による所得の場合、課税方式を納税者が選べます。
金融所得課税の引き上げはいつから?

金融所得課税の引き上げはいつから行われるのでしょうか。ここでは、金融所得課税の引き上げのスケジュールや対象者、現行制度との比較を解説します。
スケジュール
金融所得課税の引き上げは、2025年1月1日以降の所得から適用されます。2023年度の税制改正から盛り込まれていましたが、2025年から本格的に始動しました。
対象となる人
基準所得金額(年間総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額)が3億3,000万円を超え、超えた部分に対して22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超えた場合、超えている分の金額に相当する所得税が上乗せされることになります。
例えば、合計所得30億円以上の人や、株式や不動産の譲渡益だけで年間10億円以上の利益がある人は対象になる可能性が高いです。
現行制度との比較(累進課税との違い)
所得税は累進課税制度が採用されており、課税金額に応じて納付する税金も高くなっていきます。
例えば、課税所得金額が4,000万円以上の場合、最高税率の45%が課されることになります。
一方、金融所得にかかる税率は、一律20.315%です。また、金融所得にかかる税金にはすでに住民税も含まれていますが、所得税には含まれていないため10%が加算されます。
つまり、株式などの金融所得を多く保有している人のほうが税負担を抑えられるということです。
金融所得課税の引き上げが行われた理由

金融所得課税の引き上げが行われた理由として、以下の3つが挙げられます。それぞれの理由について解説します。
資産格差の拡大を防ぐため
金融所得課税の引き上げが行われた理由の1つに、資産格差の拡大を防ぐことが挙げられます。
上記でも紹介したように、金融所得にかかる税率は一律20.315%で済むため、収入がほとんど金融所得に集中している場合は税率が下がりやすくなりました。
本来申告納税者の所得税負担率は、累進課税制度によって収入が多ければ多いほど負担も上がっていきますが、所得1億円を超えてからは実効税率が下がり、高所得であればあるほど有利になります。この現象は「1億円の壁」と呼ばれています。
これでは金融所得を持っている人と持たない人で資産格差が拡大するという懸念が、以前から指摘されていました。
そこで、2025年1月から金融所得課税の引き上げがスタートしたのです。
社会保障給付費の財源を確保するため
金融所得課税が引き上げられた理由に、社会保障給付費の財源確保も挙げられます。
日本は2022年度時点で全人口の約3割が高齢者という、超高齢社会の状況です。
超高齢社会の影響を受け、国の年金や医療費、介護費用といった社会保障給付費が年々増大しています。
厚生労働省が発表した「社会保障給付費の推移」を見ると、2025年度は予算ベースで給付費総額が140.7兆円、対GDP比が22.4%でした。
2000年時点の給付費総額が78.4兆円、対GDP比が14.6%だったことから、25年間で給付費総額が約2倍、対GDP比は約1.5倍にまで増大していることがわかります。
少子化も続いている中で、今後社会保障給付費の負担はさらに増大していくでしょう。
社会保障給付費の財源は約6割が保険料、約4割が国や地方の公費で賄われています。
この保険料は総所得金額や給与所得をベースに算出されていますが、金融所得は反映されないケースもあります。
そのため、金融所得課税の引き上げで税収を拡大させ、社会保障給付費に充てようと考えている可能性が高いです。
欧米の先進主要国と足並みを揃えるため
日本では申告分離課税で一律の税率が適用されていますが、欧米の先進主要国では申告分類課税の所得額に応じて税率が変わっている国もあります。
例えば、アメリカでは所得額に応じて0%・15%・20%の3段階、イギリスは10%・20%の2段階です。
このように、アメリカやイギリスは段階的課税を採用し、最大税率を20%にしています。
一律の税率が適用されている日本が欧米の先進主要国と足並みを揃えるために、金融所得課税の引き上げに至ったと考えられます。
金融所得課税の引き上げが中小企業に影響するケース

金融所得課税の引き上げにともない、中小企業の経営者にも影響が出てくる可能性があります。ここで、中小企業の経営者に影響する可能性があるものを紹介します。
M&Aでの株式・不動産売却
金融所得課税の引き上げによって、M&Aでの株式・不動産売却にも影響してくるでしょう。
課税標準となる基準所得金額には非上場企業の株式や不動産の譲渡所得も含まれています。
M&Aで株式譲渡を行った場合、その売却益から税金を差し引いた金額が手取り額になりますが、譲渡額によっては従来よりも税負担が増えてしまい、想定していたよりも手取りが減少する可能性が考えられます。
また、買い手側も売り手側の税負担が増えることで、買収にかかるコストも上がってしまうでしょう。
だからといって税負担が上がった分の負担を売り手側に強いてしまうと、交渉が決裂する可能性もあります。
このように、金融所得課税の引き上げによって、売り手側と買い手側の双方が影響を受ける可能性もあるので注意してください。
事業承継
第三者に事業承継を考えている場合、経営者が保有する株式を第三者に譲渡することで、事業承継を行うことができます。
株式を第三者に譲渡したことで得られた利益は金融所得に該当し、その利益が高額であればあるほど税負担も大きくなってしまいます。
経営実績と継続して利益が見込める企業やブランド力のある企業、唯一の技術力を持つ企業などは企業価値も高くなり、その分譲渡益が多額になりやすいです。
中小企業でも価値の高い企業であれば、金融所得課税の引き上げが影響する可能性があります。
相続株式の売却
顧問先企業において経営者の相続人が相続税を納めるために、相続した非上場株式を発行企業に譲渡するケースもあります。
発行企業に譲渡した場合、実際に配当金は受け取っていないものの売却益で受け取ったとみなされてしまい、みなし配当として5.105~45.945%の税金が加算されることになります。
さらに、資本金の払い戻しという観点で譲渡所得になり、15.315%の税率も課せられるでしょう。
特にみなし配当は累進課税であり、得た利益が大きければ多いほど税金も高くなっていきます。
つまり、相続株式を売却した経営者もその利益が多ければその分税負担は大きくなり、さらに金融所得課税の引き上げを受けて、税負担がより大きいものになってしまうと考えられます。
ベンチャー企業の資金調達
金融所得課税の引き上げによって、ベンチャー企業は資金調達がしにくくなる可能性があります。
投資家は投資資金を回収して利益を得るために、リスクがあることも理解した上で大きいリターンを狙っていきます。
しかし、金融所得課税の引き上げによって期待できるリターンが減ってしまうことを考えると、ベンチャー企業に対する投資自体を止めてしまう人が今後増えていくかもしれません。
例えば、ベンチャー企業の経営陣が自社の株式を買収する「バイアウト」を実施した場合、株式を売却した投資家の譲渡益が対象の範囲内であれば、所得税の負担が上がってしまうことになります。
このような事態を避けるために、投資家はベンチャー企業への投資を止めてしまう可能性があります。
金融所得課税の引き上げは新NISAにも影響する?

富裕層や金融所得を多く保有する人は金融所得課税の引き上げによる影響を受けやすいですが、一方で投資信託などの金融所得を保有することになる新NISAには影響するのでしょうか。
結論からいえば、金融所得課税の引き上げは新NISAには影響しません。なぜなら、新NISAは金融所得課税の対象に含まれないためです。
ただし、全く関係がないわけではありません。これまで政府は国民に自己資産の形成を図るために投資を推奨し、NISAなどの導入も行いました。
しかし、金融所得課税の引き上げによる増税を理由に、投資を止めてしまう人が増えてしまうリスクも考えられます。
金融所得課税引き上げへの対策方法

金融所得課税の引き上げによって税負担が大きくなってしまいますが、少しでも負担を軽減するための対策方法もあります。
万が一金融所得課税の引き上げに影響する場合は、以下の対策方法も実践してみてください。
法人版事業承継税制
M&Aや事業承継は金融所得課税の対象となり、売り手側に大きな負担がかかってしまいます。
しかし、承継先が親族の場合は「法人版事業承継税制」を活用することで税負担を抑えることも可能です。
法人版事業承継税制とは、非上場株式などを贈与した際に、その贈与税について一定の要件を満たすことで猶予・免除が認められている制度です。
法人版事業承継税制には一般措置と特例措置の2種類があります。
特例措置は全株式を対象としており、納税猶予割合も80%から100%に引き上げされているなど、一般措置に比べてメリットが大きいです。
ただし、特例措置を受けるためには2026年3月31日までに特例承継計画を策定し、都道府県知事へ提出する必要があります。
一般措置であっても経営者は税負担を抑えられるため、法人版事業承継税制を活用して事業承継を計画してみてください。
エンジェル税制
ベンチャー企業やスタートアップ企業に投資をしている人におすすめなのが、エンジェル税制です。
エンジェル税制は2023年の税制改正で創設されており、株式譲渡益をスタートアップ企業などに再投資した場合、その譲渡益が非課税になるといった優遇措置が受けられます。
また、株式譲渡時に出た売却損失は、最大3年間損益通算を行うことも可能です。
個人がエンジェル税制の適用を受けたい場合、以下の要件を満たす必要があります。
-
- 投資先のスタートアップ企業が同族会社の場合、持ち株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持ち株割合を順番に加算していき、その割合が50%を超える株主グループに属していない
- 投資した企業に自らの事業をすべて承継させた個人、またはその親族などではない
- 金銭の払い込みによって株式を取得している
新NISA・iDeCo
上記でも紹介しましたが、新NISAは金融所得課税の対象には含まれていません。さらに、
iDeCoも拠出金額は全額所得控除の対象になりつつ、運用益も非課税の対象になります。
そのため、新NISAとiDeCoを活用することで、税負担を軽減しながら資産形成が可能です。
新NISAの場合、年間投資枠はつみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円の合計360万円までになります。
非課税保有限度額は生涯で1,800万円までとなっており、そのうちつみたて投資枠が600万円、成長投資枠は1,200万円です。
一方、iDeCoは拠出限度額が被保険者によって異なります。
第1号被保険者の自営業者などは月額6.8万円、第2号被保険者の会社員や公務員などは月額2.3万円または2.0万円、そして第3号被保険者の専業主婦(夫)は月額2.3万円まで掛金を設定できます。
ただし、iDeCoはあくまで老後資金を準備することを目的としていることから、原則60歳まで受給できない点に注意が必要です。
まとめ・金融所得課税の引き上げは2025年1月から適用開始!
金融所得課税の引き上げは2025年1月1日以降の所得税から適用されるため、対象者は2025年度の確定申告から税負担が増える可能性があります。
中小企業の経営者もM&Aや事業承継などで影響する場合もあるでしょう。
少しでも税負担を抑えるために、法人版事業承継税制やエンジェル税制、新NISA・iDeCoなどの活用も検討してみてください。
税金は避けられませんが、正しい知識があれば納税額を最小限に抑えることができます。創業手帳がまとめた『税金チェックシート』では、節税の基本的なポイントを整理しています。知らないまま損をしないために、ぜひ一度チェックしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)