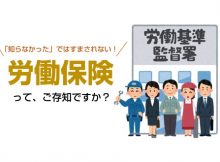労災保険とは?給付の種類や対象者、保険料率の計算方法なども解説
労災保険への加入は雇用主の義務!
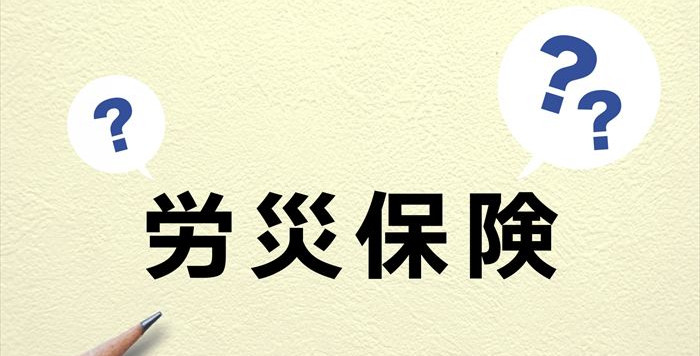
業務中に従業員がケガや病気などを負ってしまうことがあります。
このような時、労災保険に加入していることで、従業員は治療費や入院費などを負担せず、給付金によって賄うことが可能です。
労災保険への加入は、従業員を雇用する事業者の義務でもあります。
そこで今回は、労災保険とはどういったものか、給付の種類や対象者、保険料の計算方法まで解説していきます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
労災保険とは?加入義務やペナルティについて

労災保険とは、雇用されている立場の従業員が仕事中または通勤中に発生したトラブルが原因で、ケガや病気、障害、あるいは死亡してしまった場合に保険給付を実施する制度です。
労働者本人やその遺族の生活を守るために、また、被災した労働者の社会復帰を促すために用意されました。
労災保険は雇用形態に問わず、労働者を1人でも雇用している事業所には加入義務が生じます。
例えば、正社員を雇用していなくても、アルバイトを1人雇い入れている時点で、労災保険への加入義務が発生していることになります。
労働者を1人以上雇用しているにもかかわらず、労災保険に加入していない場合、「費用徴収制度」によって、労災保険から給付された金額の全額または一部の支払いが必要です。
また、労働基準法・労働者災害補償保険法を違反しているとして、懲役または罰金が科される場合もあります。
特に悪質な事業者になると、厚生労働省から社名が公表されたり、ハローワークで求人を掲載できなくなったりするので注意が必要です。
業務災害
労災保険の補償対象になるのは、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の3つです。
業務災害は、労働者が仕事中にケガや病気、障害または死亡することを指します。
ただし、あくまで行っていた業務と関係がある場合は補償対象になりますが、仕事に関係ないところでケガなどをした場合、労災保険は適用されません。
具体的には、以下のような場合は業務災害として認められます。
-
- 過重労働にともないうつ病を発症した
- 作業中に資材が崩落し、下敷きになった
- 社用車で移動していたら事故に遭った など
複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、労働者が2つ以上の事業を遂行したことで発生するケガ・病気などを指します。例えば、脳・心臓疾患や精神障害などです。
2つの企業に所属し、1日6時間ずつ・週5日勤務を続けていたら心筋梗塞を発症して倒れたといったケースだと、複数業務要因災害に認められ、労災保険の補償範囲になります。
通勤災害
通勤災害は、通勤途中または帰宅途中に起きたことが原因でケガや病気につながった状態を指します。
ただし、普段の経路とは異なる道を通っている時に起きたケガ・病気などは労災保険の対象外となるので注意が必要です。
-
- 自宅から会社に出勤している途中で、自動車同士で衝突し死亡した
- 突然の発熱によって早退し、病院で治療した後事故に遭ってしまった
労災保険における給付の種類

労災保険は補償の種類によって給付内容が異なります。
| 補償の種類 | 給付内容 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | ケガ・病気が治るまでの治療費や入院費、薬代などの給付 |
| 休業(補償)等給付 | ケガや病気が原因で働けず、賃金を得られない場合の給付 |
| 障害(補償)等給付 | ケガや病気によって障害が残った際に受け取れる |
| 遺族(補償)年金 | 従業員が死亡した際にその遺族が受け取れる |
| 葬祭給付(葬祭料) | 労働災害によって死亡した人の葬祭をするための給付 |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始から1年6カ月が経過しても治らず、障害の程度が傷病等級に当てはまり、その状態が継続している場合に受け取れる |
| 介護(補償)年金 | 障害年金または傷病年金の第1級の人すべて、または第2級の障害があり、介護を受けている場合に受け取れる |
| 二次健康診断等給付 | 脳血管や心臓を把握するための二次健康診断と特定保健指導を1年度内に1回受けられる |
療養(補償)等給付
療養(補償)等給付は、ケガや病気が治癒するまでにかかる治療費や入院費、薬代などの費用の給付です。
ここでいう「治癒」は、症状が固定化された状態(医療行為を行っても効果が期待できない状態)も含まれます。
もし症状が固定化した場合、療養(補償)等給付から障害補償給付の対象になります。
休業(補償)等給付
休業(補償)等給付は、ケガや病気が原因で働けなくなり、賃金を受け取れなくなった場合の給付です。
休業して4日目から1日あたり給付基礎日額の60%相当額、休業特別支給金として同じく休業4日目から1日あたり給付基礎日額の20%相当額が給付されます。
給付基礎日額は、労災が発生する直前の3カ月分の賃金総額(賞与は除く)を、その期間の暦日数で割った金額です。
障害(補償)等給付
障害(補償)等給付は、傷病が治癒した後に障害等級1~7級までの障害が残った際に給付される「障害等年金」と、傷病が治癒した後に障害等級8~14級までの障害が残った際に給付される「障害等一時金」にわかれます。
それぞれ障害の程度によって給付基礎日額が決まっており、さらに障害特別支給金と障害特別年金が受け取れます。
【障害等年金】
| 等級 | 給付基礎日額 |
|---|---|
| 1級 | 313日分 |
| 2級 | 277日分 |
| 3級 | 245日分 |
| 4級 | 213日分 |
| 5級 | 184日分 |
| 6級 | 156日分 |
| 7級 | 131日分 |
【障害等一時金】
| 等級 | 給付基礎日額 |
|---|---|
| 8級 | 503日分 |
| 9級 | 391日分 |
| 10級 | 302日分 |
| 11級 | 223日分 |
| 12級 | 156日分 |
| 13級 | 101日分 |
| 14級 | 56日分 |
遺族(補償)年金
遺族(補償)年金は、大きく分けて「遺族等年金」と「遺族等一時金」の2種類があります。
遺族等年金は労災事故で死亡した場合に給付され、給付基礎日額を遺族の数などに応じて支給されます。
例えば、遺族が1人だった場合は給付基礎日額の153日分、2人だった場合は201日分です。
また、遺族の数に関係なく遺族特別支給金として一律300万円、遺族特別年金として遺族の数などに合わせて算定基礎日額153日分~245日分の年金が受け取れます。
遺族等一時金は、遺族(補償)年金を受け取る遺族がいなかった場合や、失権していて受け取れない場合、さらに支給済み年金や遺族等年金前払い一時金の合計が給付基礎日額の1,000日分未満だった場合に支給されるものです。
給付額は給付基礎日額1,000日分の一時金(または支給した合計額から差し引いた金額)になります。
また、一律300万円の遺族特別支給金や、算定基礎日額の1,000日分の遺族特別一時金を受け取れる場合もあります。
葬祭給付(葬祭料)
葬祭給付は労災によって死亡した人の葬祭を行う際に、葬祭を行った人に対して給付されるものです。
給付額は、315,000円に給付基礎日額30日分を加算した金額、もしくは合計額が給付基礎日額の60日分に満たなかった場合、給付基礎日額の60日分になります。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金は、療養開始から1年6カ月経過した日、またはその日以降に傷病が治癒していないこと、傷病による障害が傷病等級に該当したことで受けられる給付です。
傷病等級が1級だと給付基礎日額の313日分、2級だと277日分、3級は245日分になります。
さらに、100万円~114万円の傷病特別支援金、算定基礎日額245日分~313日分の傷病特別年金も給付されます。
介護(補償)給付
介護(補償)年金は、障害補償年金または傷病補償年金を受給する人のうち、1級または2級の精神・神経障害、胸腹部などの臓器に障害があり、現在介護を受けていると給付されます。
給付額は常に介護を受けている場合と、随時介護を受けている場合で異なります。
常に介護を受けている場合は介護費用として支出した金額(上限172,550円)の給付です。
ただし、親族などから介護を受けていて介護費用を支出していない、または支出額が77,890円を下回っている場合、給付額は77,890円となります。
随時介護を受けている場合も介護費用として支出した金額が給付されますが、上限は86,280円です。
また、介護費用を支出していない、または支出額が38,900円を下回った場合、給付額は38,900円となります。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、直近に行われた職場の健康診断において以下すべての要件に該当した場合に、二次健康診断と特定保健指導を1年度内に1回、無料で受けられるものです。
-
- 血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIすべてに異常所見がみられる
- 脳血管疾患・心臓疾患の症状がないと認められる
- 労災保険の特別加入者ではない
労災保険の加入条件および対象者

労災保険の加入条件と対象者について、より深く掘り下げて解説していきます。
労災保険の加入条件
労災保険は、労働者を1人でも雇用する事業所は「強制適用事業所」に該当することから、労災保険への加入が必要となります。
これは正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれており、業種の規模も問いません。
ただし、5人未満の労働者を使用している農林水産事業を営む個人経営の事業所は、強制適用事業所から除外されています。
そのため、労災保険に加入していなくても問題ありません。
労災保険に加入できる対象者
労災保険に加入できる対象者は、主に被雇用者となる従業員です。
-
- パート・アルバイトを含む従業員
- 日雇い労働者
- 派遣労働者(派遣元の事業所で適用)
一方、事業所を経営する代表取締役や個人事業主は、労災保険の対象者から外れてしまいます。
なぜなら、代表取締役や個人事業主は雇用する側になるためです。労災保険は使用される側の労働者を守るための保険になるため、雇用する側は対象から外れています。
ただし、特定の条件を満たすことで個人事業主や自営業者でも労災保険への加入が認められる「特別加入制度」があります。
「特別加入者」なら個人事業主も労災保険に入れる

労災保険の特別加入制度とは、本来加入できない個人事業主や自営業者に対して、要件を満たした場合に特別加入者として労災保険に入れる制度です。
個人事業主や自営業者が特別加入制度を利用することで、万が一仕事上でケガや病気になった場合でも労働者と同等の補償が受けられます。
特に1人で事業を担っている人が休業余儀なくされてしまった場合は休業補償給付、障害が残ってしまった場合は障害補償給付などが活用できます。
労災保険の特別加入制度を利用できるのは、仕事の性質的に体を負傷しやすい事業を営む個人事業主・自営業者です。
-
- 個人タクシー業者・個人貨物運送業者など
- 大工・左官・とび職など
- 漁船による水産動植物の採捕事業
- 林業
- 医薬品の設置販売事業
- 再生利用を目的とする廃棄物などの収集・運搬・選別・解体などの事業
- 船員法第1条に規定される、船員が行う事業
また、特別加入制度の対象者は徐々に増えており、芸能関係作業従事者やアニメーション制作作業従事者、柔道整復師、歯科技工士、フリーランスなども条件を満たすことで労災保険への特別加入が認められています。
労災保険の保険料を計算する方法

労災保険の保険料はいくら支払うことになるのか気になる人も多いかもしれません。
保険料を求めるには、前年度に支払われたすべての労働者の賃金総額に、保険料率を乗じて算出されます。
保険料率は業種ごとに異なり、設定幅は88/1,000~2.5/1,000と、業種によって大きな幅があることがわかるでしょう。
例えば、小売業(保険料率3/1,000)を営んでいて2人の従業員を雇用しており、その従業員に支払っている賃金が年間350万円だった場合、労災保険料は以下のようになります。
350万円×2人×(3÷1,000)=21,000円
労災保険を申請するには?

労災保険に加入後、事故やトラブルが実際に起きてしまった際には給付金を申請することになります。
この時、事業者側はどのような手続きを行えば良いのでしょうか。ここで、労災保険を申請する流れを紹介します。
1.状況を把握する
事故が発生したらすぐに病院に搬送するか、救急車を呼ぶことが重要です。
一旦状況が落ち着いてから当事者や周りにいた従業員から話を聞き、状況を把握する必要があります。
社内にカメラを設置していた場合は、映像を確認してください。また、事故が発生した現場は立ち入り禁止にすることも忘れずに行いましょう。
なお、事故が原因で従業員が4日以上休むことになってしまった際には、労働基準監督署に「労働死傷病報告」の提出が必要です。
2.給付のための請求書を入手、作成する
労災保険の給付を受けるために、請求書を作成して労働基準監督署に提出します。請求書は補償を受ける従業員か会社の担当者が取得し、必要事項を明記していきます。
給付を受けるための請求書は素早く提出する必要があるため、ケガや病気などで本人による作成が難しい場合は、会社の担当者が作成することになるでしょう。
補償の種類によっては医療機関から傷病名や傷病の状態・経過などを記載してもらう欄もあるので、必要に応じて医療機関に連絡し、請求書を作成してください。
提出が1カ月以上遅れてしまうと、別の書類が必要となるので注意が必要です。
3.労働基準監督署に提出、調査を受ける
請求書や補償の種類ごとに必要な添付書類を揃えたら、労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署は請求内容に基づいて調査を実施し、労働災害に該当するかどうかを審査します。
例えば、従業員と災害が発生した業務の関連性や、普段の通勤ルートと事故の内容、日頃からの対応や労働環境による病気・過労死の可能性などです。
まとめ・労災保険は従業員が安心して働けるようにするための制度
労災保険は1人でも従業員を雇用している事業所なら必ず加入しなくてはならない保険制度です。
対象範囲は広く、ケガや病気に加え、後遺障害や死亡に対しても給付金が受け取れます。
労災保険は従業員が安心して働くための制度でもあるため、今後従業員の雇用を考えている人は忘れずに労災保険へ加入するようにしてください。
創業手帳(冊子版)では、経営者が知っておきたい制度に関する基礎知識から最新情報まで幅広く掲載しています。創業・起業をお考えの人やすでに起業した人も、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)