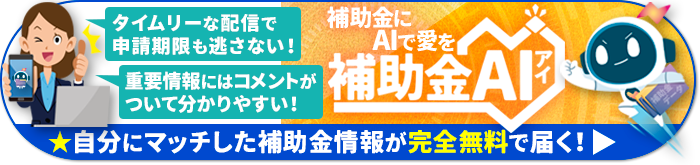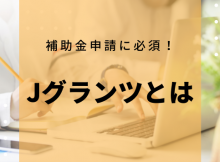補助金申請サポートの“うまい話”に注意!怪しい業者の見分け方と安全な頼り方
「補助金サポート詐欺」に騙されないためのノウハウをお伝えします

補助金や助成金は事業の成長を後押してくれる制度です。しかし、申請サポートを装った悪質業者による被害も増えています。
高額報酬や虚偽記載の強要などに巻き込まれれば、採択されても返還命令などのペナルティを負うリスクが発生するでしょう。
本記事では、怪しい業者の典型的な特徴と、契約前に確認すべき安全チェックポイント、安心して相談できる公的支援先を解説しています。
なお、本記事では「補助金」と「助成金」の両方に関する注意点を扱いますが、制度によって申請ルールや関与できる専門家が異なります。
特に「助成金」は社労士のみが申請代行できる点にご注意ください。
補助金の正しい知識があれば、トラブルを未然に防げます。創業手帳がお届けする『補助金ガイド』で最新情報を確認し、安心して制度を活用してください。無料でお届けいたします。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
「補助金サポート詐欺」が増えている背景

補助金詐欺(助成金詐欺)は、国や自治体の補助金(助成金)制度全体を悪用した詐欺行為全般です。
典型的なケースとしては、本来であれば受給資格がない補助金を虚偽の申請でだまし取るようなケースがあります。
補助金サポート詐欺といった場合には、補助金申請を餌にして事業者から高額の手数料をだまし取るような行為です。
悪質な補助金サポート詐欺が増えている背景には、補助金制度の知名度と人気が高まる半面で情報不足で困っている事業者が増えている点があります。
多くの中小企業にとって資金繰りは死活問題です。困窮している中小企業ほど詐欺業者の甘言が魅力的に響くことがあるのです。
近年は、詐欺の手口は巧妙化していて、SNS広告やオンラインセミナーを介した詐欺が増加しています。
規模が大きい企業であれば法務部門、コンプライアンス部門がある上、補助金の申請も専門部署、専門家に任せられます。
しかし、中小企業は複雑な手続きの申請を自社だけの力で行うのは困難です。
コンサルタントや外部支援を探した結果、詐欺の被害に遭ってしまうケースが増加しています。
補助金サポートの怪しい業者に共通する「うまい話」の特徴

補助金サポート詐欺を行うような怪しい業者はどこも似たような「うまい話」を持ち掛けます。ここではどういった「うまい話」を持ちかけられるのか特徴をまとめました。
ケース1:成功報酬の名目で高額請求される
20%~30%以上の相場を超える成功報酬率を設定し、採択後に過大請求する業者には注意が必要です。
成功報酬が高額になると、採択されたとしても使える補助金が少なくなってしまいます。
成功報酬の目安は10%以内です。補助金の規模によっては成功報酬が数千万になってしまうケースもあるので、上限を設けていない業者も避けてください。
最大〇〇万円といった上限を設けて適正な価格を保証している業者を探してください。
ケース2:「必ず通る」と断言される
補助金は審査基準が明示されていても、採択は公平な選考で審査されるため絶対は存在しません。
「100%採択保証」などの断言は虚偽説明に該当し、トラブルや詐欺のサインです。
審査結果は外部が保証できないものなので、「必ず通る」と断言された場合には警戒が必要です。
また、「審査機関とコネクションがある」といった宣伝も要注意となります。採択率の実績を開示していて、現実的な数字を提示している業者を選択してください。
ケース3:申請内容を事実と異なる内容に書き換えられる
申請書を業者が独断で改ざんし、事業計画と実態が乖離(かいり)するケースは注意が必要です。
虚偽の売上予測や架空の経費を記載すると、不正受給に該当し返還命令と加算金の対象になってしまいます。
申請内容は依頼者自身が最終確認し、証憑や数字の根拠も必ず把握してください。不正な内容での申請は、自社がペナルティの対象になる可能性もあります。
ケース4:審査結果前に成功報酬を請求される
審査結果が出ていない段階で成功報酬を請求するような業者は悪質である可能性が高いと考えてください。
信頼できる業者であれば、適正な着手金を設定して成功報酬も確定額から算定した適正な金額です。
加えて、交付申請をしてから審査、その後の実績報告まで一貫したサポートを提供しています。
悪質な業者では、確定額ではなく申請額ベースで審査結果前に成功報酬を請求されることがあります。
業者を探す時には、成功報酬の算出方法とどこまでのサポートが受けられるかをチェックしてください。
ケース5:会社情報・担当者情報が曖昧
業者を選ぶ時には、会社情報や担当者情報も確認します。所在地や代表者名が公式サイトや契約書に明記されない業者は信頼性が低いと考えてください。
法人登記簿や国税庁法人番号公表サイトを利用すると、実在している会社であるかどうか確認できます。
担当者の氏名や連絡先が契約書に記載されない場合、後日のトラブル対応が困難になってしまいます。必ず担当者や問い合わせ窓口を確認してください。
ケース6:社労士ではないのに「助成金のサポートをします(代行可)」と書かれている
助成金は労務管理に関わる制度が多く、社会保険労務士以外が代行すると違法です。厚生労働省は「社労士以外の助成金申請代行は違法」と公式に注意喚起しています。
代行が認められるかどうかを判断するには、業者の保有資格や登録番号で必ず確認しましょう。
社労士以外に依頼する助成金の返還などのペナルティを受けるリスクもあるので注意してください。
補助金トラブルを防ぐためにチェックしたい4つのポイント

補助金トラブルは、金銭的な損失を受けるだけでなく、社会的信用も損ねるリスクもあります。
補助金トラブルを防ぐためにチェックしてほしいポイントを4つ以下でまとめました。
1.見積書の内容や報酬体系は事前に提示されたか?
補助金のサポートを受ける時には、必ず見積書の内容と報酬体系を確認します。見積書には業務範囲・報酬額・支払い条件が明記されているかどうかチェックしてください。
中小企業庁では、契約前に複数社から見積もりを取ることを推奨しています。
見積もりをとった後は 金額だけでなく、業務の具体的内容や成果物の範囲も比較してください。」
2.契約書に金額や業務範囲が明記されていたか?
補助金サポートの契約書には報酬総額、支払い時期、業務範囲を明記しなければいけません。また、口約束だけで契約書を結ばないのはNGです。
契約書がない場合、口頭説明と異なる請求や業務放棄のリスクが高まります。
契約書の内容はすべて把握して不明点は署名前に書面で確認・修正を求めるようにしてください。
3.「行政と連携」など曖昧な説明を鵜呑みにしていないか?
補助金申請は、ほかでは使わないような用語を使用するケースがあります。そのため、あいまいな用語や説明を理解しないままに鵜呑みにしてしまうことがあります。
業者が使う「行政公認」や「特別枠」などの表現は公式制度には存在しないことが多いので、自分で確認してください。
当然ではありますが、補助金の審査は公正中立であり行政職員と個人的な関係があっても、採択に影響を与えることはできません。
あいまいな権威付け表現をしている業者は誤認誘導の可能性があるため、一次情報で裏付けをとるようにします。
4.他社と比較検討(相見積もり)を行ったか?
補助金サポート業者を初めて探す時には、相場やサービスの程度を判別しにくいです。
一社のみで即決すると、不当に高額な報酬や不利な条件で契約してしまうリスクが高まります。
複数業者から見積もりを取ることで、相場感や条件の妥当性を把握してください。
比較する時には、報酬額だけでなく、実績やサポート範囲も評価します。 安ければ良いとはいえないので、実際に話を聞いて信頼できるかどうか判断したほうが良いでしょう。
補助金について安心して相談できる支援先の例

補助金を活用して資金援助を受けたいと考えていても、補助金サポートを受けることには抵抗がある事業者もいます。
実は経験や知識も豊富で補助金についての相談ができる支援先はいくつかあります。どういった支援先があるのか以下で確認してください。
商工会・商工会議所
小規模企業や中小企業のサポートを行っている全国の商工会議所は、会員・非会員を問わず補助金申請に関する無料相談を受け付けています。
商工会、商工会議所では専門の経営指導員が制度概要や申請書作成のポイントを案内してくれるので、初めての申請でも安心して相談可能です。
さらに分野別専門家派遣(エキスパートバンク事業)では課題ごとに適切な専門家の派遣を受けられます。所在地や相談方法は日本商工会議所公式サイトで確認してください。
よろず支援拠点
よろず支援拠点は、中小企業庁が全国に設置する無料経営相談窓口で、補助金活用の助言も行っています。
中小企業診断士や税理士などの専門家が常駐し、個別課題に応じたアドバイスを提供しています。
経営に関わるあらゆる相談に何度でも無料で対応してくれて、NPO法人や社団法人、創業予定の人も利用可能です。
よろず支援拠点の予約方法や所在地は「よろず支援拠点全国本部」公式サイトで検索してください。
各都道府県の中小企業支援機関
都道府県や市区町村には独自の中小企業支援センターが設置されています。
補助金・助成金制度の案内や申請サポートを無料で受けられる場合が多いので、所轄の中小企業支援機関のサイトを確認してください。
窓口情報は各自治体の公式サイトや経済産業局ページで確認可能できます。
補助金や助成金の案内以外にもセミナーやイベントも開催されていることがあるので積極的に活用してください。
認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関は、経済産業大臣が認定した専門家機関で、補助金申請の支援実績を多数持っています。
認定経営革新等支援機関の一覧は中小企業庁公式サイトで公開され、地域や分野で検索可能です。
相談するにあたって報酬体系や対応分野は、必ず事前確認しておいてください。事業計画の外部支援に対して悪質な業者の相談も受け付けています。
怪しいと感じた時にはトラブル等通報窓口を利用してください。
「信頼できる補助金の専門家」の見極め方

補助金の申請に関わる手続きは複雑なため、外部の支援が欲しいと感じる事業者は多いはずです。
ここからはどのようにして「信頼できる補助金の専門家」を見極めればいいのかまとめました。
国家資格の有無で専門性を確認する
補助金の申請代行やサポートは様々な資格者、機関が請け負っています。まずは、どういった資格があるのか属性を確認してください。
社会保険労務士や中小企業診断士などの国家資格は専門知識と法的権限の裏付けとなります。
資格の有無は業務範囲や代行可能制度の判断基準にも直結していて、資格によって受けられるサポートの範囲が違います。
偽称でないか確かめるには、資格登録番号や所属団体を公式サイトで照合してください。
採択実績や事例紹介で信頼度を見極める
過去の採択件数や事例紹介は業者の実力を示す重要な指標です。 具体的な採択年度や補助金名が記載されている事例は信頼性が高いといえます。
いままでの実績について数値や事例が不明確な場合は、実績を誇張している可能性を考えなければいけません。
採択実績や事例紹介は、その業者がどういった分野を得意としているかを知るためにも重要です。
自社の状況に即したアドバイスがあるかで判断する
事前ヒアリングの丁寧さも信頼度判断の重要な要素です。
業者を探す時には、申請可否や採択可能性について確認し、自社の業種・規模に合わせた具体的助言があるかどうかもチェックしてください。
テンプレート的な回答しかない場合は、十分な検討や調査が行われていない可能性があります。
悪質でなくても質が悪いサポートしか提供していないかもしれないので避けたほうが良いでしょう。
報酬体系の明確さや着手金の有無をチェックする
契約を結ぶ時には、報酬額、支払い時期、返金条件が契約書で明確化されているか確認します。
採択前の高額着手金はリスクが高いので要注意です。必ず複数業者の報酬体系を比較検討してください。
中小企業庁は「報酬や費用は明確な契約書で取り決めるべき」と指導しています。これに従っていない業者は悪質であるリスクが高いかもしれません。
まとめ:補助金サポートのうまい話には焦らず冷静に判断を
補助金は先着順ではなく、制度ごとに定められた申請期間と審査基準で選定されます。
不備なく審査を通過したいと考える場合には、補助金サポートが心強い味方になるでしょう。
信頼できる情報源や公的窓口から助言を受けることが、詐欺被害防止の第一歩です。
契約後に不安を感じた場合は、消費生活センターや公的相談窓口に速やかに相談してください。
補助金の“うまい話”に惑わされないためには、正しい制度の仕組みや最新情報を知っておくことが何より大切です。
創業手帳が発行する『補助金ガイド』では、国や自治体が実施する主要な補助金・助成金をわかりやすく整理。
信頼できる情報源から、安全に補助金を活用するためのポイントをまとめています。
ぜひ、リスクを避けながら制度を味方につけるためにお役立てください。

(編集:創業手帳編集部)