最低賃金は外国人労働者にも適用される?対象範囲や雇用主が注意すべきポイントを解説
外国人労働者の雇用を検討する前に賃金設定について考えよう

最低賃金制度は、外国人労働者にも適用されます。日本で働いている労働者が対象となるため、国籍は関係ありません。
人材を雇用するにあたっては、最低賃金法によって厳しい規制が設けられています。
そのため、理解しないまま外国人を雇用し、最低賃金以下で働かせてしまえば大きなリスクを伴うので注意が必要です。
そこで、最低賃金制度の基本を解説するとともに、適用範囲や外国人労働者の平均賃金、賃金の決め方などを紹介していきます。
外国人労働者を雇う際に注意すべきポイントについても解説していくので、人材不足解消のために雇用を検討している企業や最低賃金制度について理解したい人は、参考にしてみてください。
従業員の賃金や待遇を適正に整えるうえで、活用できる助成金も存在します。
創業手帳の「雇用で差がつく助成金10選」では、雇用環境の改善や人材育成に役立つ主な助成金制度を一覧で整理しています。自社で利用できる制度の確認に、ぜひお役立てください。
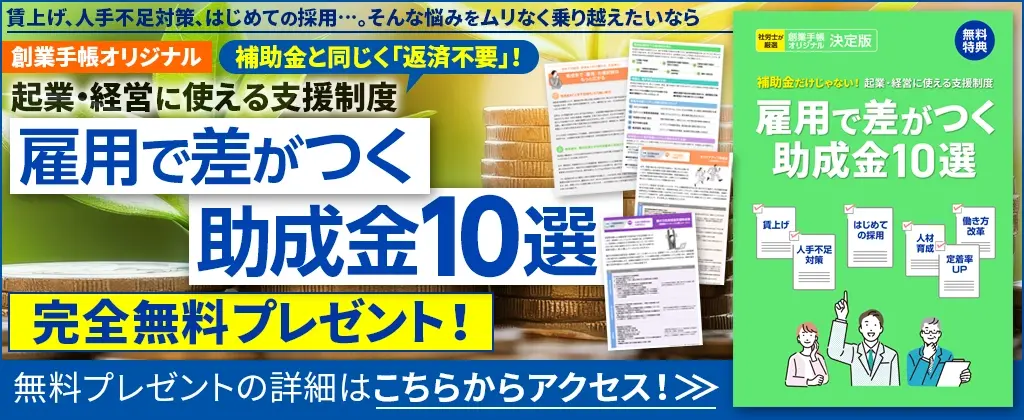
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
最低賃金制度の基本を知ろう
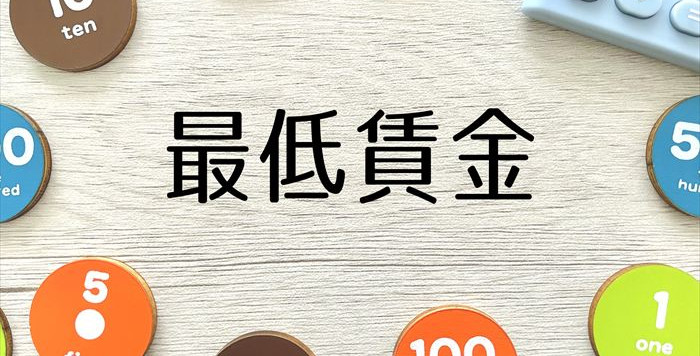
外国人労働者だけではなく、雇用を検討した際には最低賃金制度を理解しておく必要があります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低ラインを定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけない制度です。
中には、最低賃金法という法律を初めて聞いた人もいるかもしれません。
使用者が労働者に支払う給与の最低額を定めた法律で、労働者の安定した生活に加えて労働力の向上が目的となっています。
最低賃金の額は都道府県ごとに違いがあります。
最初に中央最低賃金審議会で審議され、次に地方最低賃金審議委員会に持ち込まれて額の審議を行い、最終的な判断が各都道府県の労務局長によって制定される仕組みです。
最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、両方が適用される場合には高いほうの最低賃金額以上の給与を支払わなければなりません。
地域別最低賃金とは?
産業や職種に関係なく、都道府県内にある事業場で働く全ての労働者と使用者に対して適用される最低賃金が地域別最低賃金です。
各都道府県に1つずつあるため、全部合わせると47件の最低賃金が定められています。
-
- 労働者の生計費
- 労働者の賃金
- 通常事業の賃金支払い能力
以上を総合的に勘案して定めるもので、労働者の生計費を考慮する場合には健康で文化的な最低限度の生活ができるよう、生活保護にかかる施策との整合性に配慮する必要があります。
特定最低賃金とは?
特定の産業に対して定められている最低賃金のことを言います。
各都道府県の労務局長によって地域別最低賃金は決められますが、それよりも高い額を設定すべきであると判断された場合に与えられる賃金設定です。
最低賃金審議会による調査審議を経て設定される仕組みです。2025年3月末時点では、全国で224件の特定最低賃金が定められています。
外国人労働者と最低賃金の適用範囲
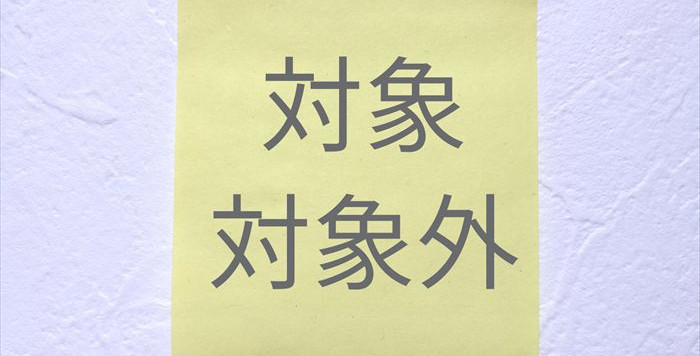
次に、最低賃金の適用範囲を確認していきます。
外国人労働者は最低賃金の適用対象
前述したように、最低賃金は日本国内で働いている全ての人が対象です。国籍に関係なく適用される制度なので、日本で暮らして働いている外国人も対象となります。
中には、日本人と異なる賃金で雇っている会社も存在しますが、定められた最低賃金以下の給与で雇用すれば、ペナルティを受ける可能性があるので注意してください。
また、派遣労働者やパートやアルバイト、期間工など、就労形態を問わずに適用される制度です。
そのため、どんな形態で働いている外国人に対しても、企業は最低賃金法を適用した額で働かせる必要があります。
技能実習生も適用対象
技能実習生とは、日本で培った技術や知識を開発途上国の人材に移転して、当該国の経済発展に寄与する国際貢献を目的とした外国人材です。
最長で5年間、日本で働きながら技能を習得します。最低賃金法は、技能実習生にも適用されます。
ただし、2024年の関連法改正を受けて技能実習制度は廃止され、新しく「育成就労制度」に移行する見込みです。
2027年から施行される予定となっており、日本の産業界において人材育成や人材確保を目的に技能実習制度の後継制度として位置づけられています。
2025年10月時点では、賃金に関する明確な新基準は定まっていないため、今後の発表に注目していきましょう。
外国人労働者が実際にもらっている平均賃金

厚生労働省による「令和6年賃金構造基本統計調査結果の概況」によると、日本で就労している外国人労働者の賃金は、日本人労働者の平均賃金330,400円と比較すると低い傾向にあることがわかっています。
平均は、242,700円となり、前年と比較すると4.3%増となっています。詳しい内容は以下の通りです。
| 在留資格区分 | 賃金 | 対前年増減率 |
| 外国人労働者 | 242.700円 | 4.3% |
| 特定技能を除く専門的・技術的分野 | 292,000円 | -1.6% |
| 特定技能 | 211,200円 | 6.7% |
| 身分に基づくもの | 300,300円 | 13.4% |
| 技能実習 | 182,700円 | 0.6% |
| その他(特定活動及び留学以外の資格外活動) | 226,500円 | -2.1% |
上記表を確認すると、技能実習生は最も低いことがわかります。前年と比較をしても0.6%しか上昇していません。
これは、日本での技能実習制度は短期間の研修が目的としているため、日本での労働者としての地位が得られにくいことが考えられます。
さらに賃金が増えることで、技能実習生の数も多くなることが予想できます。
外国人労働者の賃金の決め方

外国人を採用するとしても、賃金の決め方で悩む企業は多いかもしれません。ここでは、外国人労働者の賃金の決め方を解説していきます。
地域別最低賃金・特定最低賃金を参考にする
外国人労働者の賃金を決める方法は、基本的に日本人労働者と同じです。都道府県ごとに最低賃金が定められているため、その基準を守って給与を決める必要があります。
2025年度の地域ごとの最低賃金を見てみると、東京都は最も高く1,226円となっています。
次いで神奈川県が1,225円、大阪府が1,177円です。最も低いのは宮崎県や沖縄県の1,023円です。
最低賃金は、都道府県によって大きく差がある点が特徴です。定期的に更新もされているので、更新された後の額を遵守したうえで外国人労働者の給与額を決定してください。
上記の地域別最低賃金に当てはめると、東京都であれば時給1,226円が最低ラインとなるため、これよりも高い賃金の設定が必要です。
また、産業別特定最低賃金を参考にするのも忘れないでください。産業ごとの特定最低賃金は、地域ごとに定められています。
例えば、北海道であれば以下のように最低賃金が決められています。
-
- 処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業:1,048円
- 鉄鋼業:1,100円
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:1,049円
- 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業:1,040円
産業ごとに特定最低賃金が決められている場合には、地域別の賃金と比較して高いほうが選ばれます。
北海道の地域別最低賃金は、1,075円なので、鉄鋼業のみ特定最低賃金が選択される仕組みです。
外国人労働者の給与を決める際には、それぞれを確認してから額を決定するようにしてください。
就業規則に則って賃金を決める
地域別最低賃金・特定最低賃金を参考にする以外にも、就業規則に則って決めることも重要です。
労働者の賃金や労働時間など、労働条件に関連する職場内の規律などを定めたルールを就業規則と言います。
必ず記載する絶対的必要記載事項と事業場に定めがある際に必ず記載する相対的必要記載事項の2つがあります。
賃金に関する項目は、絶対的必要記載事項に含まれるため、必ず記載しなければなりません。
賃金の決定や計算、支払い方法、昇給に関する内容は、就業規則に明記する必要があります。
そのため、規則の内容を踏まえたうえで、賃金の設定を検討することが求められます。
雇用条件書に従って賃金を決める
使用者は、労働者との間で労働契約を結ぶ際、賃金や労働時間といった労働条件を明示する必要があります。
労働条件にも、就業規則と同じように絶対的明示事項と相対的明示事項があり、賃金は絶対的明示事項に当てはまります。
賃金の計算や支払い方法、支払い時期や昇給に関する事項は、雇用条件書にも雇用条件書にも記載が求められる内容です。
そのため、外国人労働者の賃金を決める際には、就業規則とあわせて雇用条件書の確認も欠かせません。
最低賃金額以上か確認するための計算方法

給与を決める際には、最低ラインとなる額をクリアしている必要があります。
最低額を下回っていれば最低賃金額との差額を労働者に対して支払わなければならず、対応を怠れば罰則が科せられます。
事業にも悪影響を及ぼしてしまうため、給与を決める際には確認が必須です。
ここでは、賃金が最低ラインをクリアしているか確認するための計算方法を解説していきます。
時給制
最低賃金額は時間を単位として定めているため、確認がしやすいでしょう。
「時間給≧最低賃金額」
計算式に当てはめる必要はなく、照らし合わせるだけで確認できます。
日給制
日給制で働く外国人労働者の賃金額に問題がないか調べる方法は以下の通りです。
「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額」
労働者が働く時間を所定労働時間と言います。
始業から終業までの時間から休憩を引いた時間で求めることができるため、9:00~17:00で1時間の休憩がある場合には、7時間が所定労働時間となります。
月給制
月給制の場合のチェック方法は以下の通りです。
「月給÷1カ月の平均所定労働時間≧最低賃金額」
月給制になれば、職務手当や時間外手当といった手当がついているのが一般的です。
手当は、会社や従業員によって異なる特徴があります。手当によって、計算に含めるもの・除外するものもあるので注意しましょう。
出来高払い・請負制
会社によっては歩合制と呼ばれています。計算方法は以下の通りです。
「賃金の総額÷総労働時間≧最低賃金額」
実際の成果内容に応じて賃金が支払われる形態です。タクシーの運転手や土木工事などが当てはまります。
賃金総額を総労働時間で割ることで、時給当たりの金額に直して最低ラインをクリアしているかチェックします。
上記全て組み合わさっている場合
基本給が日給で各種手当が月給制の仕組みで決められている上記を組み褪せたケースであれば、以下のように計算してください。
「基本給を時給に換算した額+各種手当を時給に換算した額≧最低賃金」
上記の計算方法を活用して時給換算し、合算した額と比較して最低ラインを超えているか確認してください。
外国労働者を雇う際に注意すべきポイント

次に、外国人労働者を雇用する際に注意すべきポイントを解説していきます。
在留資格や有効期限を必ず確認する
在留資格や有効期限をチェックすることは重要なポイントです。
在留資格で認められた活動とは異なる仕事に従事させれば、不法就労となり責任を問われるリスクがあります。
在留期限が切れていれば不法滞在となるため、雇用する前だけではなく就労中も定期的に確認することが大切です。
天引きされる金額について丁寧に説明する
日本では、所得税や社会保険料などが毎月の総支給額から天引きされるのが一般的です。
しかし、日本以外の国では個人で納めることが一般的なケースもあります。そのため、天引きシステムに戸惑う外国人もいます。
不安や疑問を与えないためにも、あらかじめ給与や賞与の仕組み、天引きのシステムをわかりやすく説明することが大切です。
福利厚生制度も理解してもらう
日本人と同様に、外国人も福利厚生の充実度はモチベーションを高めるために重要な要素です。
食事手当や住宅手当、成果に応じた報奨金など、充実させることで離職率の低下につながります。
ただし、福利厚生については利用方法を理解していないケースも多いです。制度については詳しく説明することで、メリットを感じてもらいやすくなります。
外国人労働者の賃金に関するよくある質問
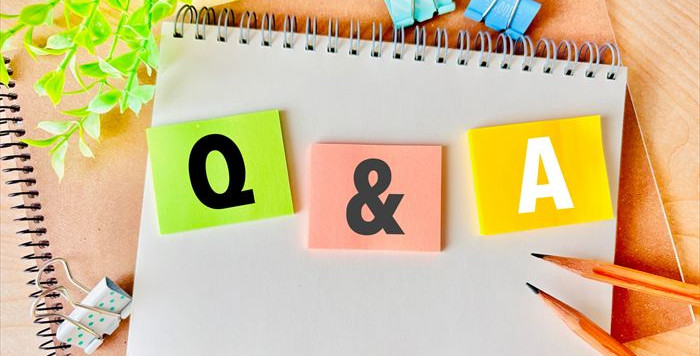
外国人労働者に対する賃金では、様々な疑問が生まれるでしょう。以下の質問に当てはまる答えを参考に、適切な額の設定を目指してみてください。
通勤手当や時間外手当は最低賃金の計算に含まれる?
最低賃金の計算では、給与に含まれる以下のものは含まれないとされています。
-
- 時間外手当
- 通勤手当
- 賞与
- 固定残業代
最低賃金を求める際には、基本給や職務手当のみが計算の対象となるので注意してください。
最低賃金を守らないと罰則を受けてしまう?
最低賃金を守らないと、違反となり罰則を受ける可能性があります。
-
- 労働基準監督署による是正勧告や行政指導
- 未払い分を支払う義務
- 50万円以下の刑事罰
また、技能実習計画の認定取り消しや新規受け入れの禁止といった制裁を受ける可能性もあります。
違反企業名が公表されれば、社会的信用も大きく損なわれてしまうので注意してください。
「同一労働同一賃金」も適用される?
同一企業で働く正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す制度が同一労働同一賃金です。同一労働同一賃金は外国人労働者にも適用されます。
同じ業務内容にも関わらず、「外国人だから」「非正規雇用だから」と待遇に差をつけると同一労働同一賃金に反すると判断されてしまいます。
従業員側から損害賠償請求をされたり、労働基準監督署などから行政指導・是正勧告を受ける可能性があるため注意してください。
まとめ・外国人労働者に選ばれる職場体制・環境を構築しよう
最低賃金は、国籍に関係なく適用されるため外国人労働者も対象です。外国人労働者の多くは、日本人以上に待遇を重視する傾向にあります。
母国よりも高い給与を求めて来日する人も多くいるため、日本の最低賃金よりも低い額で働くことがわかれば、選ばれない会社となってしまいます。
雇用する際には給与や待遇を合理的に決めて、わかりやすいように伝えたうえで雇用契約を結びましょう。
外国人労働者にも選ばれる職場づくりには、適正な賃金だけでなく、教育・定着への投資も欠かせません。
創業手帳の「雇用で差がつく助成金10選」では、人材育成や処遇改善に使える各種助成金情報をまとめています。制度を上手に活用し、安心して働ける環境づくりにお役立てください。
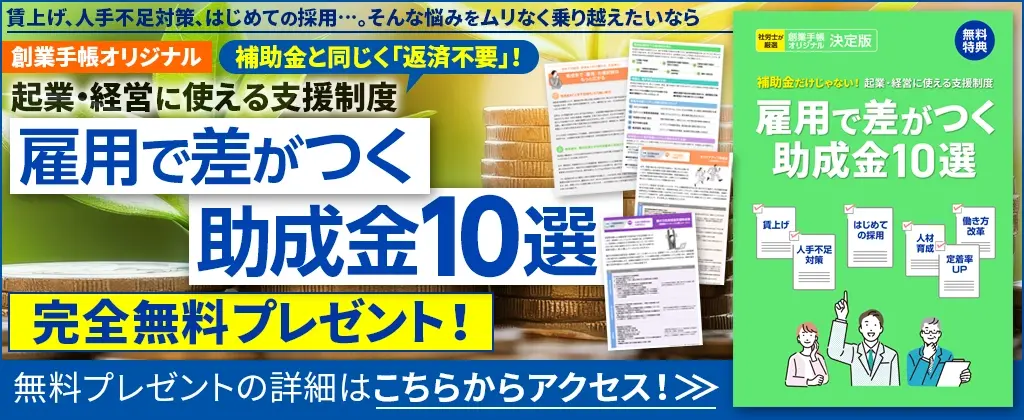
(編集:創業手帳編集部)




































