条件によっては傷病手当金をもらえないケースもある ケガや病気で働けなくなると十分な収入が得られずに生活が難しくなるケースがあります。そのような時の支えとなるのが...続きを読む

人事とは、企業内において企業の運営方法等、基本的なルールを考えだし又実際に運用をしていく職種の事である。
企業によりその業務内容には差異が出てくるが、基本的には給与の計算や健康保険・雇用保険等の管理、従業員の健康診断の手配や人事データの管理等、事務職の総括の様な業務が主となる。
大企業の場合人事データ等は外部に管理依頼する場合があるが、その場合には労務はその窓口担う場合が多い。
主に、事務作業の全般の管理を担う為に多用なスキルを求められるが、特に社会保険労務士の資格や一度労務の業務を経験したことがある人が重用されやすい職種でもある。

条件によっては傷病手当金をもらえないケースもある ケガや病気で働けなくなると十分な収入が得られずに生活が難しくなるケースがあります。そのような時の支えとなるのが...続きを読む
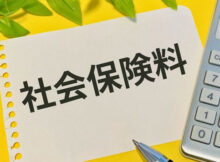
会社にとって大きな負担となり得る社会保険料 社会保険料は日本に住んでいる人が病気、ケガ、高齢などを理由に生活困難になった場合などのリスクに備えて分担し合う公的な...続きを読む

人事評価システムを導入して問題解決を目指そう 人事評価システムを導入すれば、従業員の業績やスキルなどを客観的に把握するために役立ち、評価や管理などを徹底できます...続きを読む

個人事業主にも条件によって就業規則の作成が義務付けられている! 個人事業主として事業を運営している中で、「個人事業主も就業規則は必要なのか?」と疑問に感じる人も...続きを読む

業務委託と最低賃金の関係を理解して報酬トラブルを防ごう フリーランスや副業の広がりにより、「業務委託」という働き方を選ぶ人が増えています。 しかし、業務委託と雇...続きを読む
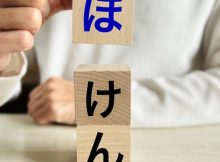
個人事業主は国民健康保険組合に加入できる! 日本では、国民皆保険制度によって国民全員が健康保険に加入できるようになっています。 企業に勤めていればその会社の健康...続きを読む

外国人労働者の雇用を検討する前に賃金設定について考えよう 最低賃金制度は、外国人労働者にも適用されます。日本で働いている労働者が対象となるため、国籍は関係ありま...続きを読む

フリーランスは業務委託契約について理解しよう フリーランスは、特定の団体や組織、企業などに属さず、専門的なスキルや知識を活かして働くことを意味します。 しかし、...続きを読む

元ハローワーク職員が、求人票作成のポイントや効果的な使い方をわかりやすく紹介 ハローワーク(公共職業安定所)は、無料で求人を掲載できる国の機関です。求人票の作成...続きを読む

働き方の多様化に伴ってダブルワーカーは増加傾向 副業解禁の流れを受けて、複数の会社で働くダブルワーカーが増えています。 ダブルワークの場合、社会保険の加入パター...続きを読む

労災保険の特別加入制度を利用すればお仕事で怪我や病気になった際のリスク軽減が可能です 労働災害(業務や通勤が原因で負傷したり病気になったりすること)は、法人役員...続きを読む

就業規則・契約書の明示に役立つ「所定労働時間」の基本知識 従業員を雇う側は、労働時間に対する確実な把握が重要です。また、所定労働時間は会社によってルールが異なる...続きを読む

リベンジ退職で企業が深刻なダメージを負う可能性がある 「会社を辞めたい」と感じたことがある人もいるでしょう。 本来なら退職手続きを済ませる人も多くいるかもしれま...続きを読む

様々な企業で給与改定の動きが進んでいる 近年、様々な企業においてボーナスの給与化が進んでいます。ボーナスがなくなれば生活にも影響が出ると考える人も多いでしょう。...続きを読む
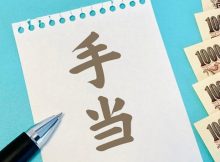
「傷病手当金」と「傷病手当」は似た言葉でも目的が異なる 仕事や日常生活の中で病気やけがによって働けなくなった時、収入の不安を少しでも軽減する制度が「傷病手当金」...続きを読む

有給休暇を取得しやすい仕組みを作ろう 「年次有給休暇」は、労働者に対して付与することが労働基準法で定められています。 会社ごとに決められている方法に従って申請し...続きを読む

秋採用はスピードと魅力発信が鍵! 就職活動と聞くと春からはじめて夏頃に終わるイメージがあるかもしれません。 しかし、秋は求職者が再び動き出す採用チャンスです。 ...続きを読む
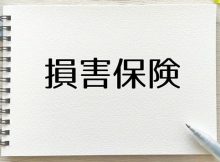
損害賠償のリスクに備えるなら損害保険 企業活動には、事故や災害などの様々なリスクがあります。想定外の損失が起きれば事業継続が難しくなることも考えられます。 リス...続きを読む

個人事業主でも従業員を雇って事業を拡大しよう 事業の拡大によって人材不足が懸念される場合には、個人事業主でも従業員を雇うことが可能です。 しかし、従業員を雇用す...続きを読む
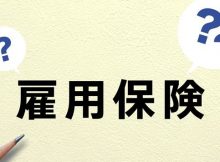
原則フリーランスは雇用保険に入れない ケガや病気などによって仕事ができなくなってしまった場合、会社員なら雇用保険に加入していることで、失業中・休業中の給付支援を...続きを読む

仕事と不妊治療の両立をサポートする方法はさまざま 厚生労働省の調査によると、不妊治療を受けている従業員の26.1%が「仕事との両立ができない」と回答しています。...続きを読む

中小企業の事業主・役員も計画的に老後へ備えよう 役員退職金とは、代表取締役や取締役など、役員に対して支給する退職金です。通常の労働者に対して支給する退職金とは異...続きを読む

自社の信頼を損なう悪質な「タイミー営業」が問題に スポット的に従業員を雇用できる「スポットワーク」「スキマバイト」を活用している事業主の方もいるのではないでしょ...続きを読む
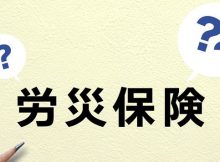
労災保険への加入は雇用主の義務! 業務中に従業員がケガや病気などを負ってしまうことがあります。 このような時、労災保険に加入していることで、従業員は治療費や入院...続きを読む

企業と従業員の損失を防ぐために介護離職対策は必須 日本には、約10万人もの介護離職者がいます(総務省 令和4年就業構造基本調査結果の要約より)。働ける能力と意思...続きを読む

時短正社員のメリットやデメリットを知って導入を検討しよう 時短正社員は、フルタイム正社員よりも短い時間で勤務する働き方です。時短正社員を導入することで、社員は育...続きを読む

定年後の再雇用は企業側にメリットあり! 少子高齢化社会の日本において、すでに労働力を確保するのが難しく、人手不足に陥っている企業も少なくありません。 しかし、高...続きを読む

従業員のための制度を理解しよう はぐくみ企業年金は、確定給付型の企業年金制度です。はぐくみ企業年金を導入することによって、企業は掛金負担を抑えながら福利厚生の充...続きを読む

若手人材の確保のために「奨学金返還支援制度(代理返還)」が注目 奨学金返還支援(代理返還)制度とは、企業が従業員の奨学金を代わりに返済する制度です。2021年よ...続きを読む

人材派遣を利用する前に平均単価や相場を知っておこう コストをできるだけ抑えつつ人材を確保したい場合には、正社員雇用ではなく人材派遣サービスを選ぶ人もいます。 し...続きを読む